既存住宅売買瑕疵保険とは?!

既存住宅売買瑕疵保険ってなに?
既存住宅とは
中古住宅(戸建・マンション)の意味。
瑕疵とは「キズ」のこと。
既存住宅売買瑕疵保険とは、
住宅購入後にトラブル(雨漏れ、給排水トラブルなど)が発見された場合、
負担してくれる保険です。
「加入は義務?」

新築戸建&マンションは
10年間保証する瑕疵担保の加入義務があります。
しかし、中古住宅は売主が業者or個人で異なり、加入は任意です。
宅建業者販売タイプと個人間売買タイプ
①宅建業者販売タイプ:売主が宅建業者の場合
例えば、不動産屋が倒産して
瑕疵担保責任を負えなくなった場合、
購入者は保険会社に請求できます。
売主が業者の場合は、契約不適合責任の期間が2年あります。
特約で勝手に短くしたり、
免責(保証なし)にすることはできません。
②個人間売買タイプ:売主が個人の場合
個人の契約不適合責任は3か月間が一般的です。
その期間、
保証を受けることで買主さんへの負担を代わりにしてもらえます。
今回の記事は、個人間売買タイプのほうを解説します。
既存住宅売買瑕疵保険の加入費用は?

中古住宅(戸建・マンション)により、加入金が異なります。
※個人間の売買タイプです。
既存住宅売買瑕疵保険にかかる費用は
「保険料+検査料」です。

■保険料:約2~5万円
■検査料:約5~11万円
保証期間が長くなるほど、値段がアップします。
合計約7万円~16万円ほど
既存住宅かし保険のホームページを参考にすると、値段などわかります。
【既存住宅売買かし保険(個人間売買タイプ)のポイント】
①既存住宅売買かし保険は、
「売主が宅建業者の場合」と「売主が宅建業者以外(個人間売買)の場合」の商品があります。
②構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などで、保険期間は5年間または1年間です。
③万が一、引渡しを受けた建物の保険対象部分に瑕疵が見つかった場合は、その補修費用をまかなうことができます。
既存住宅売買瑕疵保険の支払対象は?

①補修費用
②調査費用
③転居、仮住まい費用など

・ドアの建付けが悪い
・換気扇が壊れた
・給湯器の調子が悪い
などは対象外です。
※ただしオプション契約で
給湯器故障が対象になるケースも

なるほど。
住宅設備は保証対象外なのか・・・
補償対象となる主な部位と内容
| 内容 (補償される瑕疵の例) | |
| 構造耐力上主要な部分 | 基礎、柱、梁、壁、屋根などに構造上の欠陥がある場合(例:傾き、ひび割れ、倒壊の危険など) |
| 雨水の浸入を防止する部分 | 屋根、外壁、開口部(窓・ドア)からの雨漏りなど |
| 給排水管路 (オプション) | 室内の給水・排水管、接続部分からの漏水 (※保険商品によってはオプション扱い) |
| 給排水設備 (オプション) | 浴室・トイレ・キッチンの配管設備の漏水や故障 (保険会社やプランによる) |
<保険期間&保険金を支払う場合
の事象例>
・構造耐力上主要な部分 5年間 または1年間・基本耐力性能を満たさない場合
・建築基準法レベルの構造耐力性能を満たさない場合
・雨水の浸入を防止する部分 防水性能を満たさない場合
・ 雨漏りが発生した場合
給排水管路※通常有すべき性能または機能を満たさない場合
(設置工事の瑕疵による)水漏れ、逆勾配
給排水設備・電気設備※ 機能が失われること
(設置工事の瑕疵による)設備の機能停止
参照元:住宅瑕疵担保責任協会より参照
補償対象外になるケース
・経年劣化や自然損耗
(時間とともに劣化しただけのもの)
・中古住宅購入後の入居者の故意・過失による損傷
・外構(塀・門扉・庭など)
・地震、洪水、台風などの天災による被害(※一部保険では天災特約あり)
保険金&保証期間
保険金支払額=(修補費用等-5万円)×100%
保証期間は「1年」 or「5年」
長いほど費用が高くなります。

個人売主の場合、
契約不適合責任が3か月のため、
1年あれば十分です。
住宅設備は対象外?
既存住宅売買瑕疵保険は
給湯器、給水器、空調設備、
換気扇など、住宅設備は保険対象外です。
既存住宅売買瑕疵保険の加入条件は?

既存住宅売買瑕疵保険に加入するためには、
住宅診断にパスすることです。
ホームインスペクションともいわれ、
戸建は約10万円、マンションは約7万円ほど支払うことで
有資格者が、基礎や屋根裏、床下など非破壊で目視確認します。

非破壊って、
壁とか壊さないってこと?!

そうです。
サーモグラフィなど機器を使いますが、基本的に何も壊さない検査です。
そのため、完璧な住宅検査ができるわけではありません。
住宅診断で瑕疵があったら?
指摘された箇所を補修する必要があります。
※指摘箇所を補修をしないと、保険に入れません
また、調査機関によりますが、
新耐震基準を満たしていないとNGなケースもあります。

小修繕レべルならいいですが・・・
仮に100万円かかる修繕の場合(屋根や外壁の補修など)は、瑕疵保険に入るよりも、
家の売値を下げて、不適合責任免責にする方法もあります。
保証会社は何社あるの?
<有名な保証会社一覧>
・住宅あんしん保証
・日本住宅保証検査機構(JIO)
・住宅保証機構
・ハウスジーメン
・ハウスプラス住宅保証
既存住宅売買瑕疵保険のメリットは?

既存住宅売買瑕疵保険のメリットを解説します。
買主が安心して購入しやすい
既存住宅売買瑕疵保険は費用をかけ、
修補などをし、検査に取った安全性の高い物件と証明できます。
そのため、買主にとって、安心して購入できるメリットがあります。
税制優遇が受けられる
既存住宅売買瑕疵保険へ加入すると、
複数の税制優遇が受けられます。
<複数の税制優遇>
・住宅借入金等特別控除
(住宅ローン控除)
・特定のマイホームを買い換えたときの特例(買い換えの特例)
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
・登録免許税の税率の軽減措置
・不動産取得税に係る特例措置
※手続きについては税務署&税理士に確認願います。
既存住宅売買瑕疵保険に加入すると、
保険証券とは別に「保険付保証明書」を受け取ります。
その書類をエビデンスとして、
優遇を受けられため紛失に注意しましょう。
既存住宅売買瑕疵保険のデメリットは?

既存住宅売買瑕疵保険のデメリットを解説します。
事前の建物検査が必要
保険をかける前に、専門機関による
「インスペクション(建物状況調査)」が必須。
検査に通らなければ保険加入できません。
また、検査費用+保険料を合わせると、
5万円〜10万円以上になる場合があります
(※ケースによる)

加えて修理費が発生する場合もあり
補償対象が限定的
構造耐力上主要な部分や雨漏りに限られ、
外構や経年劣化によるトラブルは対象外。
加入できない場合がある
築年数が古すぎる、
修繕履歴が不明などの場合は保険加入が断られることがある。
補償期間が限定的
通常1年〜5年(多くは2年)の補償期間。
長期にわたって安心できるわけではない。
既存住宅売買瑕疵保険の加入の流れ

①ホームインスペクションを受けるか提案
※不動産会社が媒介契約時に業者をあっせん(紹介)してくれます。
※戸建約10万円 マンション約7万円ほど
※任意です。強制ではありません。
↓
②検査を受け、合格する
検査は1日以内に終わり、合格すれば完了です。
瑕疵が見つかった場合、検査基準に合格するように修補し、再検査が必要になります。
※戸建は100万単位の修理もあり
↓
③保険に加入
ホームインスペクション検査に合格すると、
瑕疵保険の加入の契約を締結します。
※保証は引き渡し日に設定する
ケースが多いです。
既存住宅売買瑕疵保険って実際加入者は多い?

結論から言うと、まだまだ加入は少ないです。
※全体の30%~40%が加入
中古の戸建
ホームインスペクション代&保険料金だけでも、20万円以上かかります。
また、瑕疵が見つかると、修補する必要があり、費用負担が重くなります。
※修補が長期間の場合、引き渡しが遅れることも

「面倒だしいいや」となるケースは
少なくありません。

検査、修理、再検査、
瑕疵保険加入・・・
って時間もお金もかかるのね・・・
中古の区分マンション
区分マンションはほぼ未加入です。
加入するメリットが少ないからです。
瑕疵保険のトラブル1位は雨漏れ、のため、
マンションの雨漏れは外壁や屋上になります。
つまり、
共有部分は管理組合の修繕費用で賄うため、
加入費用が余計にかかるだけです。

区分マンションも完璧ではなく、
給排水管だけは、少し心配です。
特に70~80年代のマンションの購入はご注意を・・・
まとめ

□宅建業者販売タイプと個人間売買タイプ
既存住宅売買瑕疵保険は2種類ある
□既存住宅売買瑕疵保険の加入費用は?
■保険料:約2~5万円
■検査料:約5~11万円
保証期間が長くなるほど、値段がアップします。
合計約7万円~16万円ほど
□既存住宅売買瑕疵保険の支払対象は?
・補償対象となる主な部位
構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分
・補償対象外になるケース
購入後の入居者の故意・過失による損傷
地震、洪水、台風などの天災による被害
住宅設備など
□実際加入者は多い?
まだ少ない。
調査、修理、再調査、保険加入と
時間とお金が意外とかかる
| 加入メリット | 加入デメリット | |
| 安心感 | 購入後に重大な欠陥が見つかっても補償される | 対象外のトラブルも多く、 過信は禁物です。 |
| 資産価値 | 保険付き住宅として売却時に有利になる場合あり | 検査基準が厳しく、 加入できないケースも |
| 買主の保護 | 欠陥があった場合、修繕費や調査費が補填される | 補償範囲が限定的で、 全てのリスクをカバーできない |
| 信頼性の可視化 | 第三者による検査済みという証明になる | インスペクション・保険料 修理費用など コストが高額になることも |
| 利用可能物件 | 宅建業者・個人間売買どちらでも利用可能(条件あり) | 古い物件では そもそも対象外となることも |
既存住宅売買瑕疵保険にかかる費用が気になるあなたの
お役に立てれば幸いです。
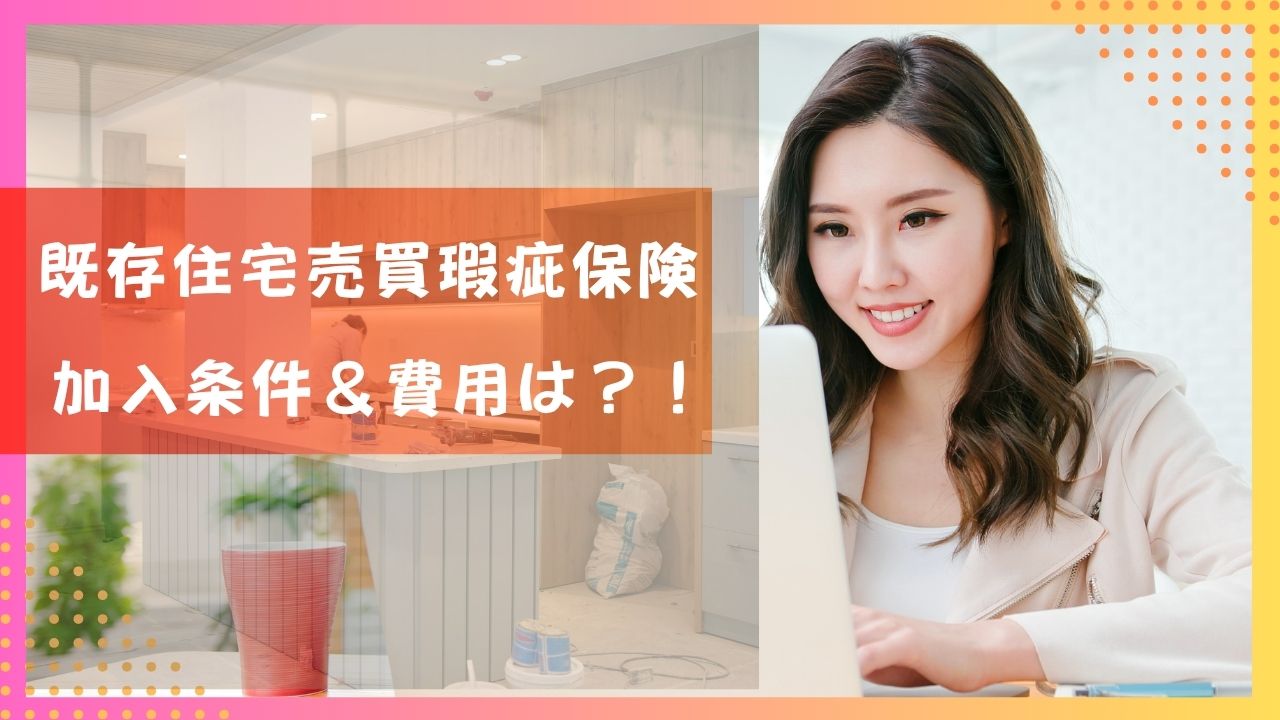




コメント