持ち回り契約の基礎

持ち回り契約って正直どうなの?
不動産の持ち回り契約とは、不動産の売買契約など締結する際に、対面などで手続きを経ず、
書面や電子メールなどを回覧して合意を形成し契約を成立させる方法を指します。
通常は売主・買主双方対面し、契約書を交わしますが
コロナの影響で対面を避ける事例が増えました。
持ち回り契約は、
不動産売買で売主・買主が同席せずに、
契約書を「郵送」や「手で持ちまわる」などで署名押印する契約です。

通常は売主・買主双方対面し、契約書を交わしますが
コロナの影響で対面を避ける事例が増えました。
売主様→買主様の順番でご契約
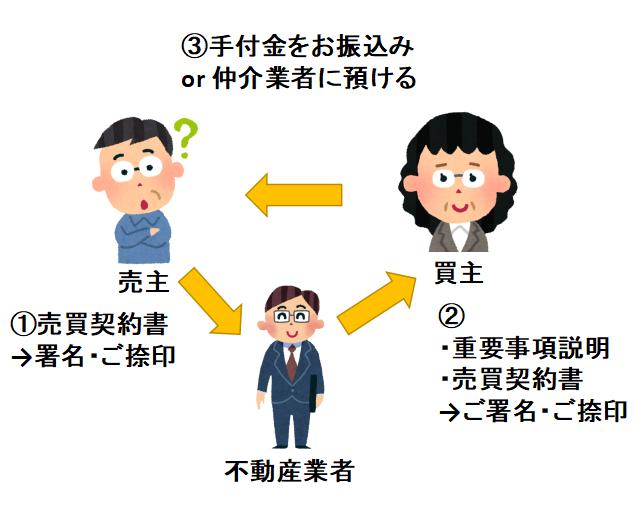
<売主様が先の持ち回り契約>
①売主様:売買契約書をご記入
②買主様:売買契約書をご記入
③手付金を振込 or 担当者が預かる
④担当者が売主様へ振込 or 手渡し
一般的には、売主様に最初に契約書をご記入いただくことが多いです。
買主様→売主様の順番でご契約
<買主様が先の持ち回り契約>
①買主様に重要事項説明&売買契約書をご記入
②手付金を預かる or 振り込みを保留
③売主様が売買契約書にご記入
④手付金を渡す or 振り込みをする
持ち回り契約:メリット・デメリット
持ち回り契約:メリット・デメリット
を比較表にしました。
| メリット | デメリット | |
| コスト | ・会場費や交通費などのコストを削減できる | ・郵送代や書類管理コストがかかる場合がある |
| 柔軟性 | ・当事者の都合に合わせやすい | ・当事者の対応が遅れると全体の進行が滞る |
| 時間管理 | ・直接会わなくても契約が可能なため、日程調整の手間が省ける | ・契約締結までに時間がかかる (郵送・確認・押印に時間を要する) →担当者が直接伺う方法あり |
| 安全性・ 信頼性 | ・各当事者が自分のペースで内容確認・検討できる | ・書類の紛失・改ざんリスクがある ・信頼関係がない場合は不安 |
| 契約内容の確認 | ・内容をじっくり確認できる | ・内容変更があった場合、面倒 |
| 法的トラブル回避 | ・慎重に進めることで法的なミスを防ぎやすい | ・署名・捺印の順序や方法に不備があると、 契約の効力に問題が生じる可能性 |
持ち回り契約のケース

持ち回り契約の具体的なケースを紹介します。
①コロナ・足腰が悪いなどで立ち会えないケース
病気の影響で「売買契約に立ち会えない」場合
持ち回り契約はよく使われます。

売主さんが病気・ご高齢で足腰が悪いなど。
買主さんに売買契約書に署名捺印いただき、営業マンが、売主宅で契約書に署名捺印していただきます。
②遠方のケース
例えば、群馬県の田舎の実家を
「東京の息子さん」が相続し、買主が群馬の場合。
東京から群馬に行くことが面倒なので、持ち回り契約になるケースがあります。
※買主さんに署名捺印いただき、東京へ足を運ぶか、郵送で記載していただきます。
③ワンルームマンションなど投資案件のケース
例えば、福岡の人が東京の1Rマンションを売却するときは、持ち回りになります。
※賃借人が居住中で、オーナーチェンジ
決済は司法書士が代理人として、
処理をするケースが多いです。

遠距離なので、やや危険な気もしますが、上記の方法で仲介をしている会社さんは多いようですね。
④低価格は不動産のケース
500万円などややお安めの不動産の場合は、
売主さんが対面で契約することは少ないです。
事前に契約書に持ち回りでサインしてもらうことが多いです。
また、抵当権が未設定で、現金払いのため、
その日に所有権移転も含め「完結するケース」もあります。
⑤離婚など家庭問題のケース
離婚後の財産分与や相続問題など家庭の事情によるケース。
不動産を処分する際、夫婦一緒だと気まずくなりますよね・・・
持ち回り契約は買主・売主が先なの?

持ち回り契約はどちらでもOKです。
ただし、物元が契約書や調査をすることが多いため、
売主側に記名、捺印を2通してもらい、買主側に渡すケースがスムーズです。

逆に買主様のキャンセルを防ぐために、買主側に先に記載してもらうケースもあります。
理由はシンプルでドタキャンは買主側が多く、
重説と契約を済ませ強くグリップするためです。
<売主先行のやり方>
①契約書2通、売主が記名捺印をし、日付は未記入
→買主へ返送 or 担当が持ち帰り
②買主が契約書2通、記名捺印をし、日付は記入
→手付金を売主へ振り込む
③買主に1通のみ売主へ返送か、 担当が持ち帰る
<買主先行のやり方>
①重要事項説明書の交付&説明、売買契約書を郵送or持参
②契約書2通、記名捺印をし、
日付は未記入、返送 or 担当が持ち帰り
③手付金(預かり)を不動産屋業者へ振込み
④後日、売主に売買契約書を発送or持参
※2通に記名捺印、日付を入れる
⑤買主に1通のみ返送、営業が持参
不動産屋→売主に手付金を振り込む
※買主→売主へ指定日に直接振込みも可能
決済・引き渡しはどうする?
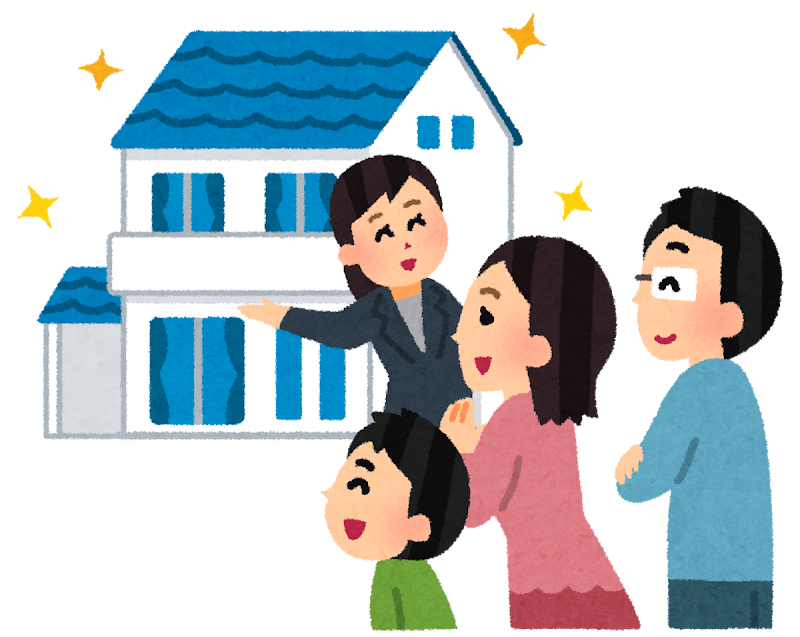
原則、決済&引き渡し日には売主・買主双方立ち合いが必要です。
ちなみに、司法書士を代理人とすることで決済することは可能です。
また、抵当権が抹消済みだったり、金額が安価な場合は、
事前に売主さんから司法書士が書類を預かり、着金確認で所有権移転登記をすることも可能です。
司法処理に代理する場合の手順

- 事前相談・委任契約の締結
- 売主または買主が司法書士に連絡し、代理人としての依頼を相談。
- 必要書類や手続きの流れ、費用について説明を受ける。
- 委任状を作成し、司法書士に代理権を付与
- 本人確認と書類準備
- 司法書士が売主・買主の本人確認を行い、登記書類(登記申請書、登記原因証明情報など)を準備。
- 売主が不在の場合、事前に司法書士と面談して署名・押印を済ませる
(代理人に委任できない作業) - 必要書類:印鑑証明書、権利証(登記識別情報通知)、委任状など。
- 司法書士が売主・買主の本人確認を行い、登記書類(登記申請書、登記原因証明情報など)を準備。
- 決済当日の対応
- 司法書士が決済に立ち会い、書類の真正性や売買意思を確認。
- 売買代金の振込、領収書交付、鍵の引き渡しを代理人が代行
(銀行や不動産会社の応接室など) - 司法書士が登記に必要な書類を最終確認し、問題なければ代金決済を許可。
- 司法書士が決済に立ち会い、書類の真正性や売買意思を確認。
- 登記手続き
- 決済後、司法書士が法務局で所有権移転登記や抵当権抹消登記を申請。
- 登記完了後、登記事項証明書を取得し、名義変更の確認を行う。
- 決済後、司法書士が法務局で所有権移転登記や抵当権抹消登記を申請。
- 完了報告
- 司法書士が依頼者に手続き完了を報告し、必要書類(登記事項証明書等)を引き渡す。

売主・買主が入院中だったり、遠方などの場合は便利です。
ちなみに、売買契約は持ち回りでもよいですが、
決済&引き渡しは可能であれば、
当人同士顔を合わせることをおすすめします。
まとめ

持ち回り契約のメリット・デメリットをまとめました。
| メリット | デメリット | |
| コスト | ・同席契約に比べて会場費や交通費などのコストを削減できる | ・郵送代や書類管理コストがかかる場合がある |
| 柔軟性 | ・当事者の都合に合わせて進められる | ・当事者の対応が遅れると全体の進行が滞る |
| 時間管理 | ・直接会わなくても契約が可能なため、日程調整の手間が省ける | ・契約締結までに時間がかかる (郵送・確認・押印に時間を要する) →担当者が直接伺う方法あり |
| 安全性・ 信頼性 | ・各当事者が自分のペースで内容確認・検討できる | ・書類の紛失・改ざんリスクがある/信頼関係がない場合は不安が残る |
| 契約内容の確認 | ・内容をじっくり確認でき、弁護士等と相談する余裕がある | ・内容の共有や修正がしにくく、変更があった場合は全体に影響が及ぶ |
| 法的トラブル回避 | ・慎重に進めることで法的なミスを防ぎやすい | ・署名・捺印の順序や方法に不備があると、契約の効力に問題が生じる可能性 |

遠方でない限り、
担当者が書類を持参するケースが多いです。
もしくは、電子契約書を利用する方法があります。
※収入印紙代が0円です。
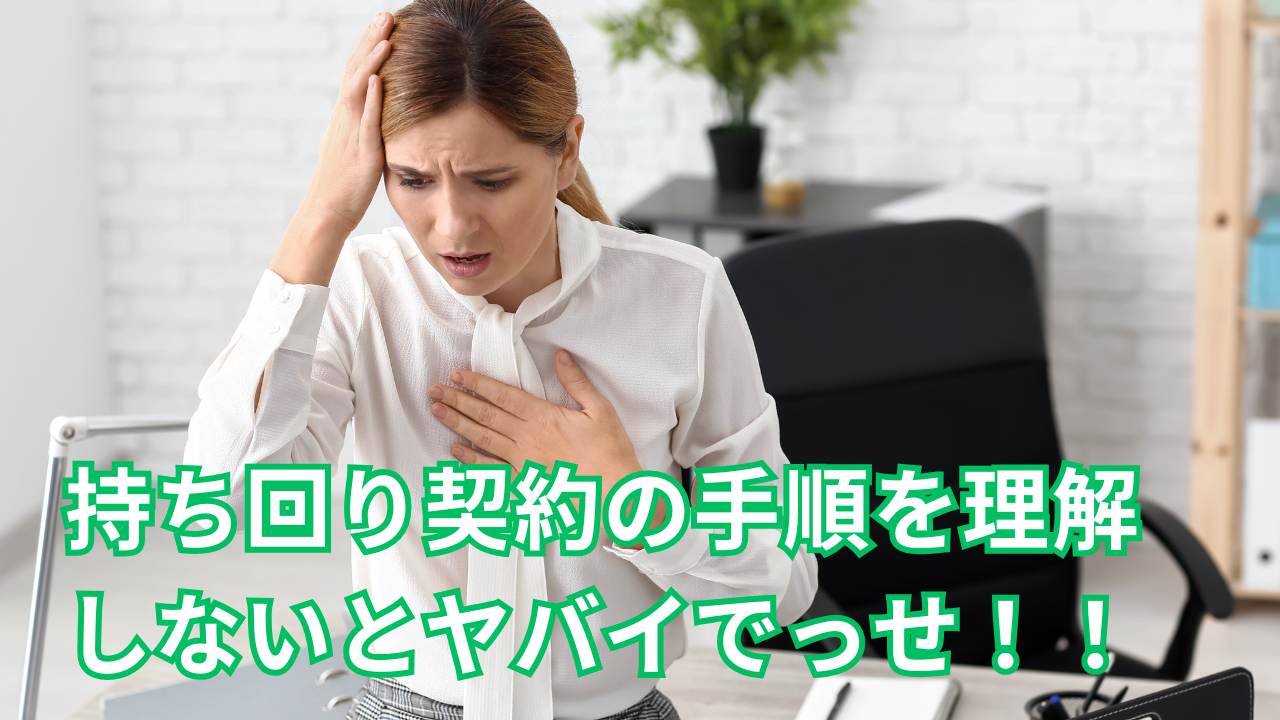


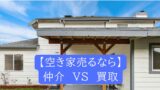



コメント