
土地を売りたいけど、
道路って大切?

ある意味、
土地よりも「道のほう」が重要といえます。
今回は土地を売る前のよくある
「道路」についてQ&A形式で回答します。
【境界問題編】はこちら↓↓↓
【道路編】土地を売る前のよくある疑問Q&A!

Q:公道と私道の違いは?
| 公道 | 私道 | |
|---|---|---|
| 所有者 | 国・都道府県・市区町村などの公的機関 | 個人または民間 (複数人で共有の場合も) |
| 管理者 | 道路管理者 (市区町村) | 所有者 (個人または共有者) |
| 通行の自由 | 誰でも自由に通行可能 (道路法に基づく) | 一般的には通行可能だが、制限される場合もありうる |
| 維持・修繕費用 | 原則、行政が負担 | 所有者が負担 (補助金が出る場合も) |
| 建築許可との関係 | 原則として建築基準法上の「接道要件」を満たす | 条件を満たせば「建築基準法第42条2項道路」などとして扱われる場合あり |

公道と私道だと、
売れる金額に差が出るの?

私道は安くなりがちです。
公道(市道、県道など)の場合は、
深く悩む必要がありません。
一般的な査定差の目安(住宅地の場合)
| 公道接道 | 私道接道 |
|---|---|
| 査定価格:100% | 査定価格:70%~90% ※持ち分ゼロだと安くなりがち |
査定額が下がる主な理由(私道の場合):
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 通行・掘削の権利 | 上下水道・ガス管の埋設に制限があると価値が下がる |
| 将来の修繕費 | 私道の維持費を自費で負担する必要がある可能性 |
| 車両進入の制限 | 幅員が狭い私道は再建築や車両通行に不利 |
| 再建築の可否 | 私道が建築基準法上の「道路」として認定されていないと、建築許可が下りないことがある |
Q:私道って何種類あるの?建築基準法上の道路じゃない?
| 私道の種類 | 法的根拠 | 内容・特徴 |
|---|---|---|
| 位置指定道路 | 建築基準法第42条1項5号 | 開発行為などで市町村の指定を受けた私道。 建築基準法上の道路として認められ、再建築可能。 宅地造成地によくある。 |
| 42条2項道路(みなし道路) | 建築基準法第42条2項 | 昭和25年以前からある幅員4m未満の道。 将来の拡幅を前提に「道路」とみなされ、再建築が可能。 セットバックが必要なことも。 |
| 法定外道路 (赤道など) | 不明確(昔からの通路) | 昔から存在するが、道路法の管理外。 市町村の管理であることが多いが、用途や通行に制限がある場合あり。 |
| 単なる私道 (非道路) | 法的指定なし | 法的に「道路」として認定されておらず、原則として建築不可。再建築や通行に大きな制限がある。 |

たくさんあるのね。
実際に見てみたいわ!

googleマップで見てみましょう。
①位置指定道路
南道路で隅切りが両端にあります。
②42条2項道路(みなし道路)
左手の平屋の全面が広がっています。
※基準線(中心)から2メートル後退が必要。
③単なる私道
ストリートビューでは、中へ入れません。
筆者は歩いたことがありますが、途中から砂利道で、大地主が密集しているエリアでした。

私道って、建築基準法上の道路じゃないの?

いえ。
位置指定道路と42条2項道路(みなし道路)は建築基準法上の道路です。
また、開発業者が100%持ち分の現場などは42条1項2号で、再建築できるケースもあります。
| 種類 | 建築可能性 | 道路認定 | 通行の自由 | 所有者 |
|---|---|---|---|---|
| 位置指定道路 | ◯ | ◯ | △ (同意必要なことも) | 個人または共有 |
| 42条2項道路 | ◯ (要セットバック) | ◯ | △ | 個人または共有 |
| 法定外道路 | △ | × | △ | 国・市町村など |
| 非認定私道 | × | × | × | 個人 |
Q:家の目の前が私道で持ち分なし。売れますか?
売れますが、相当安くなる覚悟が必要です。
| 条件 | 再建築の可否 | 解説 |
|---|---|---|
| 私道が建築基準法上の道路 (例:位置指定道路) | △ 条件付きで可能 | 通行・掘削承諾があれば可能なケースあり |
| 私道が建築基準法上の道路でない(通路や赤道など) | ❌ 建築不可 | 再建築できない。 43条但し書き許可が必要な場合も ※難易度が高い |
| 私道が「みなし道路(42条2項)」かつ接道2m以上ある | △ セットバックすれば可能 | 所有者の同意が求められることも |
<再建築可能にする対策>
| 方法 | 解説 |
|---|---|
| 私道の持ち分を購入・分与する | 一部を取得できれば確実に再建築可能に近づく |
| 所有者から通行・掘削承諾書を取得 | 融資や建築確認の条件を満たす代替手段として有効 |
| 自治体の「但し書き許可」を取得 | 43条但し書きにより、例外的に建築許可される可能性あり |
Q:赤道、青道ってなに?
| 意味 | 主な用途 | 現在の取扱い | |
|---|---|---|---|
| 赤道 | 昔の登記簿で、里道 赤いインクで記載していたことに由来 | 人や家畜が通る通路など (※細い道) | 国・市町村の管理が多いが、 民有地として誤って登記されていることもある |
| 青道 | 水路を青いインクで記載していたことに由来 | 農業用水、排水路など | 埋め立てられて宅地になっていることもあるが、 法的には「水路」扱いの場合あり |
| 赤道(里道) | 青道(水路) | |
|---|---|---|
| 登記の有無 | 原則、登記されていない | 原則、登記されていない |
| 所有者の記載 | 登記簿には「所有者なし」か「国(公有地)」とされる | 同上 |
| 地番の有無 | 地番がない場合が多い | 地番がない場合が多い |

道路台帳や水路台帳で調べられます。

赤道、青道のデメリットは?

境界確定の費用が高額になります。
※公道と比べ20万円以上プラスになるケースあり
Q:法定外公共物ってなに?
| 項目 | 法定内公共物 | 法定外公共物 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 道路法、河川法などの法律に基づく管理対象 | 法律に基づかないが従来から公共的に使われてきた土地 |
| 代表例 | 国道、県道、市道、準用河川、都市公園 | 赤道(里道)、青道(水路)、農道、用排水路、墓地道など |
| 管理者 | 国・都道府県・市区町村の道路管理者や河川管理者 | 市町村などが慣習的に管理 (財務省が所有する場合も) |
| 登記 | 登記簿が整備されており、所有者が明確 | 登記されていないものが多く、地番や所有者の記載がないことが多い |
| 利用目的 | 明確な法律上の目的(通行・河川・公園など) | 地域住民の通行、水利、農作業道などの地域的な用途 |
| 扱い | 公共事業対象・補助金ありなど、法的整備が進んでいる | 建築制限や払い下げが必要なことも多く、トラブルが生じやすい |
| 払い下げ (民有化) | 原則として困難(国有財産として厳格に管理) | 条件を満たせば用途廃止・払下げ申請により民有地化が可能 |
Q:家の目の前が幅広い水路、再建築できない?
再建築不可になります。
・・・と言いたいですが、できるケースがあります。
12メートル道路に水路があります。
コンクリの橋の向こうにアパートが建築されていますが、なぜでしょうか。

「建築物の敷地は、原則として幅4m以上の道路に、
2m以上接していなければならない」
ってことは未接道じゃないの?

再建築不可のため、建物が建てられません。
しかし、道路にも「敗者復活戦」があります。
それが、ただし書き道路です。
※建築基準法第43条のただし書きに基づいて、建築できない土地でも、
特別に建築が認められるケースを指します。
建築基準法 第43条
原則: 建築物の敷地は、建築基準法に定める道路に2m以上接しなければならない。
但し書き:
「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、この限りでない。」
👉 この「但し書き」による例外で建築が許可される土地が「但し書き道路に接する土地」ということになります。

なるほど!
なんでも再建築不可じゃかわいそうだから、
特別に許可があれば再建築できるのね!

もちろん、許可がでればですが・・・
ちなみに、売却査定をすると、かなりお安くなってしまいます。
建築審査会次第ですが、許可目安として、近所で水沿いに建築されていれば、
高確率で建築できるといえます。
査定額の下落幅(目安)
| 地域・条件 | 査定価格への影響 |
|---|---|
| 都市部(例:東京23区) | 通常の価格の 70~80%(20~30%減) 例:通常5,000万円 → 3,500~4,000万円 |
| 地方の住宅地 | 60~80%程度になることも(20~40%減) |
| 狭小・変形・通行困難など複合要因あり | 最大50%以下に評価が落ちるケースもある |
Q:目の前の道が1.7メートルしかない。再建築できる?
目の前の道の幅が1.7メートルしかない場合、
その道は「建築基準法上の道路」に該当しない可能性が高い。
※建築不可(再建築不可)となるケースが多い
| 方法 | 解説 |
|---|---|
| セットバック | 道路が「42条2項道路」(みなし道路)の場合、 敷地の一部を後退(セットバック)すれば建築可能なことも |
| 但し書き許可申請 | 建築基準法第43条但し書きに基づく許可。 行政が「安全上問題なし」と認めた場合に限り建築可能になる |
| 隣地と一体利用 | 隣接地と合わせて接道距離を確保できれば可能なケースも(※合筆や共有が必要) |
Q:旗竿地の価値はどれくらい下がる?
旗竿地は通常の整形地(正方形・長方形)と比較して、
10%〜30%程度安くなるのが一般的です。
※条件次第では最大40〜50%程度下がることも。
<評価が下がる主な理由>
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| ■ 接道条件が悪い | 通路が細く、道路にしっかり面していないため利便性・視認性が低い |
| ■ 建築の自由度が低い | 車の出入り、建築プラン、重機の搬入などに制限が出やすい |
| ■ 採光・通風が悪くなりがち | 周囲が家に囲まれ、日当たりや風通しが劣ることがある |
| ■ 分筆・再販が難しい | 将来的に売却しにくく、資産性が下がる |
| ■ 通路の管理・所有問題 | 私道や持ち分のない通路が絡むと、再建築や通行にリスクが出る |
Q:北と南に道路がある。北側は公道で接道義務は果たしている。南はみなし道路。再建築時は、セットバックは必要?

片方が公道で接道条件を満たしているから
、南道路のセットバックは不要では?

ケースによります。
建築基準法第42条2項の規定により、南側道路に面して再建築をする場合は、
たとえ北側で接道義務を満たしていても、南側が2項道路であればセットバックが必要です。
<セットバック不要なケース>
・都市計画区域外
・建築物が南側道路に全く接していない(敷地境界が離れている)
・建築物が北側道路側にしか建たない、南側に構造物を設けない
・敷地の形状や位置的に、南側道路が敷地の一部に該当しない

不動産屋さんに確認してもらいましょう。
自治体や特定行政庁によっては、みなし道路について、
将来的な道路拡幅や安全確保のためにセットバックをお願いするかも?
※法令上の必須要件ではなく、行政指導の範囲であることが多い
Q:水道管や下水管が隣と越境している/されている場合の注意点は
1. 【所有関係・設置状況の確認】
- 越境している配管が誰の所有物かを明確にする(自分・隣人・自治体・水道局)
- 図面や登記簿、上下水道台帳でルートや管理主体を確認。
2. 【同意の有無・文書化】
- 越境が黙認で行われていた場合、トラブルに
- 現状で問題がないとしても、「越境同意書」や「覚書」などの明文化する
3. 【修理や更新時のトラブル】
- 配管が破損・老朽化した際に、隣地に立ち入らないと修理できないケースがある。
- トラブル時に「誰が責任を負うか」「費用負担は誰か」などが曖昧だと揉める。
4. 【売却時に影響】
- 越境があると、売却時に告知義務があります(契約不適合責任の対象に)。
- 買主が敬遠することもあるため、早めに解消・明文化しておくのがベスト。
| 状況 | 対応方法 |
|---|---|
| 越境されている | ①確認と境界調査 ②「越境管使用の同意書」取得 ③撤去を求めるか、 賃料・使用料を請求することも可 (要法的検討) |
| 越境している | ①お隣の許可を得る (文書化) ②将来的に移設できるか検討 ③売却前には告知+同意書が望ましい |
| お互い黙認 | ・文書で合意を取っておく(将来のトラブル回避) ・できれば個別引込にする |

個別の新規配管の引き込みは50万円~かかるケースもあり、
「金銭的に難しい」
と断られるケースも。
このあたりは、個別性が強いため不動産屋さんと相談して
売却活動をしましょう。
まとめ

【道路編】土地を売る前のよくある疑問Q&A!売主必見!
について解説しました。
次は、土地売却時、お隣さんとの「境界」について解説します。
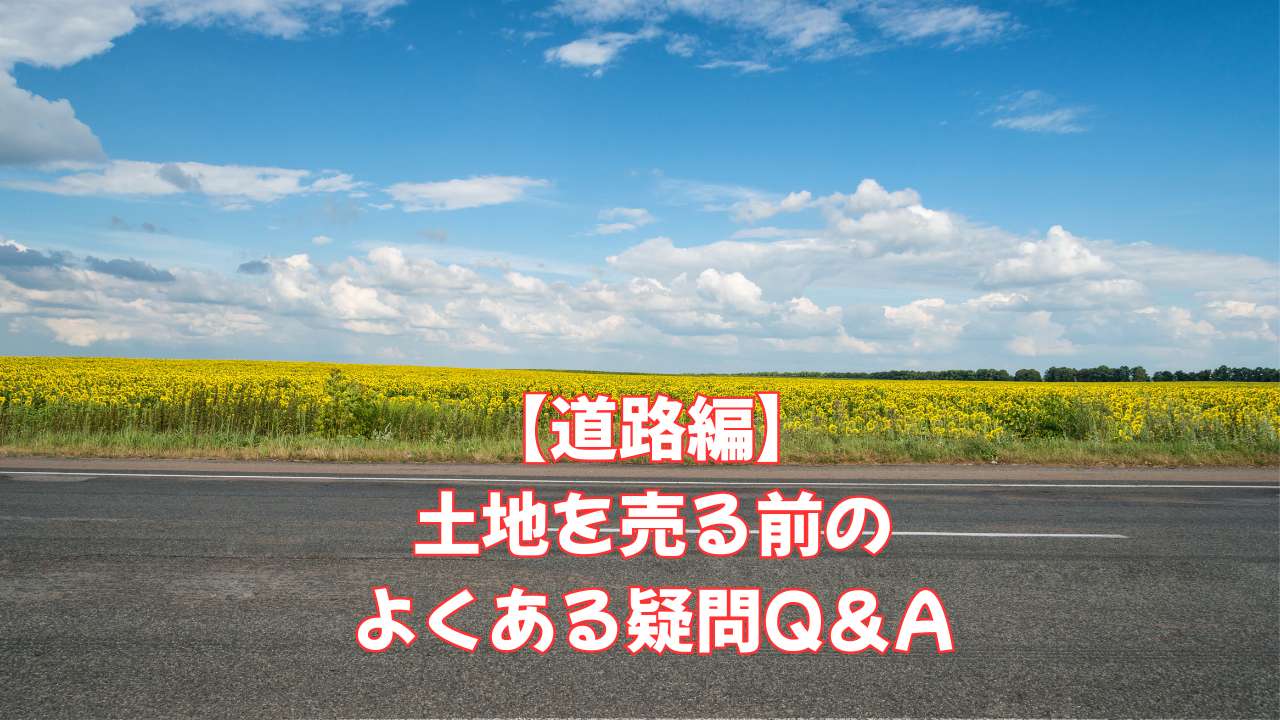

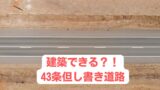


コメント