
私の土地、埋蔵文化財包蔵地かも・・・
売りづらいって聞いたけど、
実際、どうなの?

売却は可能です。
ただし、メリット&デメリットを把握しないと、
トラブルになるおそれがあります。
【記事作成の引用元】
文化庁の文化財について
e-Gov法令検索 (e-Gov Legal Search) – 文化財保護法
伊勢崎市埋蔵文化財保護課
埋蔵文化財包蔵地ってなに?
埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち)とは、
地中に土器や石器、古い神社や住居跡など、
“昔の文化財”が埋まっている可能性がある土地のことです。

日本全国におよそ46万カ所あり、
年間約9,000件の発掘調査が行われています。
簡単に言えば、土地を掘ると、土器やハニワが出てくるかも・・・
という土地ですね。
✅ メリット(長所・いいところ)
- 歴史的価値がある
自分の土地で歴史的な発見があるかもしれないというワクワクがあります。
また、文化財として価値が認められると、まちづくりや観光資源として注目されることもあります。 - 相続税・固定資産税の控除が受けられる可能性
発掘調査にかかった費用は、相続税の評価から控除できる場合があります。
また、一定条件を満たすと固定資産税の軽減対象になる可能性もあります。
※自治体やケースによって異なるため注意を - 自治体の補助が受けやすいケースもある
住む家を建てる場合には、自治体が発掘調査費用を補助してくれることがあります
(※居住用住宅に限る)
※アパートは事業用のため、補助金はでません。 - 埋蔵文化財に配慮した活用が可能
発掘調査の必要がある場所を避けて建物を配置するなど、
工夫次第で手間や費用を減らせることがあります。
❌ デメリット(短所・困るところ)
- 売れにくく、価格も下がりやすい
埋蔵文化財包蔵地は、
「工事が遅れるかもしれない」
「費用がかかるかも」
といった理由で買い手がつきにくく、安くなりがち。
開発や建築工事をするときは、
着工の60日前までに自治体(教育委員会)や文化庁長官に届出が必要です。
調査・報告が義務付けられると、工期が遅れるケースも。 - 調査費用の負担が重いことも
本採掘調査には100万以上かかることがあり、個人で住宅を建てる場合は自治体が一部を補助するケースもあります。
※アパートは事業用建築では自己負担です。 - 建て替え・ローン審査に影響
将来的に建て替えを考えているとき、埋蔵文化財包蔵地であると届出や調査が必要になり、計画が頓挫することもあります。
また、金融機関によっては埋蔵文化財包蔵地を懸念してローンの審査がやや厳しくなります。 - 買い手が敬遠しやすい
工期の遅れや費用負担などが理由で、「面倒」「価値が小さいかも」と
敬遠する人がいるため、やや流通しにくい傾向があります。
💡 「売れない」問題をどう乗り越える?

事前調査をして安心材料に
土地を売却前に自治体や教育委員会へ問い合わせて
①遺跡台帳に載っているか
②過去に発掘調査されたか
を確認し、記録をそろえておきましょう。
台帳に載っていなければ、調査義務も不要になります。

ネット上で簡易的に調べる方法もあります。
例えば、マッピングぐんまの「遺跡・文化財」では、
群馬県内にある周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)が調べられます。
建物の履歴調査
過去に建築された建物がずっと問題なく使えていた場合、証拠を集めて提示すれば、買い手の安心感を高められます。
重要事項説明で丁寧に説明
不動産契約時に「埋蔵文化財包蔵地」であることを説明するのは義務ですが、
ていねいに説明すれば、買い手の理解を得やすくなります。
埋蔵文化財包蔵地の査定額はいくらくらい?

埋蔵文化財包蔵地の査定額は、
同じエリア・条件の「通常の土地」より1割ほど低く評価されることが一般的です。
以下、市街化区域で60坪(約198㎡)の土地を例に、ざっくりとした相場と査定イメージを説明します。
■前提条件
- 所在地:市街化区域(=建物が建てられるエリア)
- 面積:60坪(=198㎡)
- 相場価格:坪単価30万円(仮定)
→ 通常の土地なら 60坪×30万円=1,800万円
■埋蔵文化財包蔵地だった場合の査定額
| 減額率 | 査定額(おおよそ) | 備考 |
|---|---|---|
| 減額なし(0%) | 1,800万円 | ※珍しい、既に調査済み等 |
| -10% | 約1,620万円 | 軽度の制限あり・情報開示済 |
| -20% | 約1,440万円 | 届出や調査の可能性あり |
| -30% | 約1,260万円 | 調査費用のリスクが高い・ 売れにくい |
| -50%以上 | ~900万円以下 | 工事制限・重要遺跡の可能性あり |
査定に影響する具体的要素
- 過去に建物が建っていたか?
→ 古家が建っていた場合、調査済み。
「建築可能」と判断され、減額が少ない。 - 遺跡台帳に登録されているか?
→ 教育委員会の調査で
「埋蔵文化財包蔵地に該当」とされると、
届出義務が発生し、マイナス要因。 - 調査負担を買主が引き継ぐか、売主が担うか
→ 誰が費用を負担するかによっても大きく査定が変わります。
💡ワンポイントアドバイス
- 事前に「遺跡台帳」に載っているかを確認
→ 市区町村の教育委員会や役所で調べられます。
非該当であれば減額なしで売れる可能性も。 - 「調査済証」や「建築記録」があれば提示する
埋蔵文化財包蔵地のよくあるQ&A

Q1. 埋蔵文化財包蔵地ってどうやってわかるの?
A:市区町村の教育委員会(文化財保護課など)で確認できます。
「遺跡地図」や「文化財台帳」に載っているかを調べてもらうことで判明します。
インターネットで公開している自治体も増えています。
Q2. 発掘調査って誰がやるの? 費用は?
👉A:調査は主に自治体や指定業者が行い、費用は原則として土地の所有者が負担します。
ただし、個人住宅を建てる場合は自治体が一部~全額を補助するケースもあります
※市町村による
試掘は教育委員会などが負担する自治体もあります。
Q3. 調査が必要かどうかは、どうやって決まるの?
👉A:建物の位置や基礎の深さなどに応じて、自治体が判断します。
- 地面をあまり掘らない建物:調査なしでOKになることも
- 深い基礎や地盤改良工事をする場合:調査が必要になりやすい
Q4. 過去に建物が建っていた土地でも調査が必要?
A:調査済みであれば、再調査は不要なことが多いです。
ただし、建物の位置や規模が変わると再調査になる可能性があります。
Q5. 調査にどれくらい時間がかかる?
👉A:1週間〜数カ月。規模や遺物の量によって異なります。
簡易な「試掘調査」だけなら数日〜1週間程度、
大規模な発掘になると2〜3カ月かかることもあります。
Q6. 発掘された文化財って誰のもの?
A:原則として国(または自治体)のものになります。
個人が所有することはできません。
発掘されたものは保存や展示の対象になります。
Q7. 埋蔵文化財包蔵地は相続税や固定資産税で優遇されるの?
A:発掘調査費が相続財産から控除されることがあります。
また、固定資産税が一部減額されるケースもありますが、自治体ごとに制度が異なります。
Q8. 売却時に「埋蔵文化財包蔵地」であることは説明しないとダメ?
A:不動産の重要事項説明で必ず伝える必要があります。
知らずに売ってしまうと、告知義務違反となり、損害賠償の恐れがあります。
❓Q9. 埋蔵文化財包蔵地の調査の流れを簡単に教えて
① 調査の必要性を確認
- 市区町村の教育委員会(文化財課など)に、
「この土地で工事をするけど、埋蔵文化財包蔵地に該当しますか?」と確認
→ 台帳に載っていなければ、調査不要で終了!
②文化財包蔵地だったら「届出」提出
- もし該当していたら、「埋蔵文化財発掘の届出書」を提出(文化財保護法に基づく手続き)
- 建築予定の60日前までに提出する
③教育委員会が「調査の要否」を判断
- 建物の規模・深さ・位置などを元に、「調査が必要かどうか」判断
④ 必要な場合は「試掘調査」(軽い掘削調査)
- 小規模に地面を掘って、遺物の有無や深さを確認
- 通常は1日〜数日で終わる
- 遺物が出なければ→そのまま建築OK!
→慎重に工事を始めましょう
⑤遺物が出たら「本調査」(発掘)
- 石器や土器などが出てきた場合、本格的な発掘へ
- 数週間〜数カ月かかることも
- 調査後は建築OKになる(調査の義務を果たせばよい)
本調査は費用が発生するため、
売買契約の特約に
「本採掘指示がでたら白紙解除」
の項目を入れておくことで、買主側が安心します。
✔︎ まとめ

| 観点 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 歴史的価値 | 🟩 文化財として価値がある可能性 | 🟥 売却価格が下がりやすい |
| 税制・自治体 | 🟩 相続控除や調査補助の余地あり | 🟥 調査費用・工期に不安あり |
| 取引面 | - | 🟥 買い手に敬遠されやすい |
| 利用・建築 | 🟩 配慮した計画で回避可能 | 🟥 60日前届出・調査義務がある |
| 資金調達 | - | 🟥 ローン審査で不利になる場合も |
埋蔵文化財包蔵地は「売れない」と言われることもありますが、工夫次第では売却可能です。
- 事前に調査してリスクを減らす
- 建築履歴など安心材料を準備する
- 重要事項説明を丁寧にする
- 最悪の場合には専門買取業者に依頼する
これらをしっかり準備すれば、「売れる土地」になります。

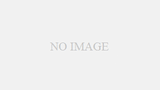

コメント