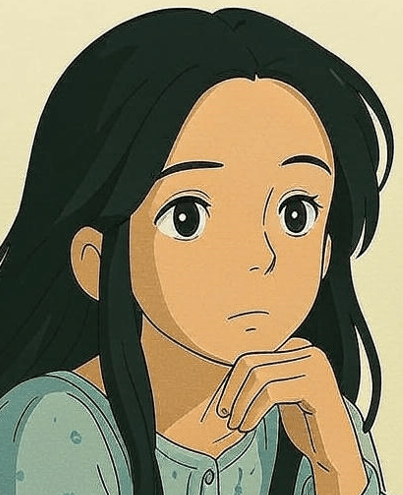
家を購入したとき、住宅用家屋証明書の説明があったんだけど・・・
よくわからない!!

今回は、住宅用家屋証明書について解説します。
Shimo log 司法書士 下大輔さんのちゃんねるより参考
住宅用家屋証明書とは?
住宅用家屋証明書とは「個人」が自己の住宅用家屋の
①所有権の保存登記(新築)
②所有権の移転登記
③抵当権の設定登記
に係る登録免許税の軽減を受ける際に必要な証明書です。

手数料は、証明書1枚につき1,300円ほどです。
簡単に言うと、不動産の購入したりすると、税金がかかります。
その税金がお安くなりますよ~という書類です
注文住宅、建売、中古住宅の取得や名義変更、抵当権設定などで登記する際に減税になります。
適用要件は?
以下、住宅用家屋証明書の発行適用要件を解説します。
①新築又は取得した者が自己の居住の用に供する家屋であること。
②当該家屋の床面積(登記事項証明書上)が50平方メートル以上であること。
③当該家屋が区分所有建物である場合は建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物または低層集合住宅であること。
④新築の住宅の場合は新築後1年以内、建築後未使用の住宅(建売住宅・分譲マンション)または建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記している
中古の場合は?
- 要件:
- 個人が自己の居住用として取得する家屋。
- 床面積が50㎡以上。
- 取得後1年以内に登記申請を行う。
- 建築後20年以内(耐火建築物は25年以内)、
または新耐震基準に適合していること(耐震証明書が必要)。
- 軽減内容:
- 所有権移転登記の税率:通常2.0% → 0.3%。
- 抵当権設定登記の税率:通常0.4% → 0.1%(一定の条件を満たす場合)。
誰が証明書を取得するの?
自分でやる場合は、自分で役所で申請します。
ですが、一般的にはハウスメーカー司法書士さん、
中古の場合は買主の司法書士さんがやるケースが多いです。

不明な場合は、ハウスメーカーさんや仲介業者さんに質問しましょう。
登録免許税率は?
<登録免許税率>※不動産評価額に税率をかけます。
中古建物:2%→0.3%
新築建物(保存登記):0.4%→0.15%
抵当権設定登記:0.4%→0.1%
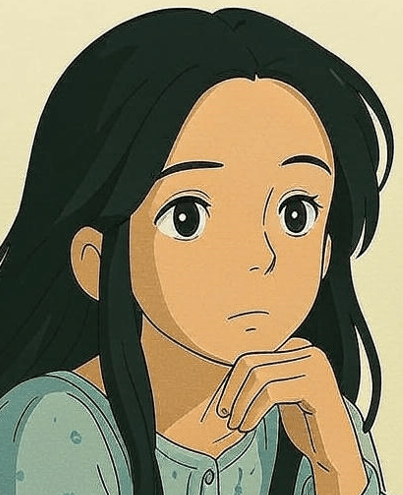
うーん難しい・・・
1500万円の中古戸建(ローン1500万円)を実例を出して解説します。
<通常>
□1500万円×2%=30万円
□ローン1500万円×0.4%=6万円
→総合計:36万円
<住宅用家屋証明書>
□1500万円×0.3%=4.5万円
※「土地は対象外」で不動産評価額の2%
□ローン1500万円×0.1%=1.5万円
→総合計:6万円

住宅家屋証明があると、36万円→6万円減税されました。
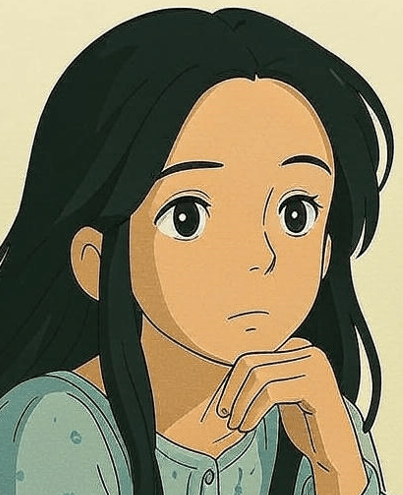
すごい!30万円くらい安くなるの!
建物表示登記と保存登記とは?
| 【建物表示登記】 | 【所有権保存登記】 |
| どんな不動産?(スペック) 例:木造、瓦屋根、100㎡ | 持ち主は誰? |
| 法律上の義務 | 他人に対抗できる |
| 税金はかからない ※代行費用は発生 | 税金がかかる ※代行費用は発生 |
建物表示登記は、「建物が完成した」と国に報告する義務があります。

建物が建築したから、1か月以内に登記が必要です。
所有権保存登記は「この不動産は誰が持ち主なのか?」
を登記し、第三者に対抗ができます。
※赤ちゃんの出生届けと似ています。
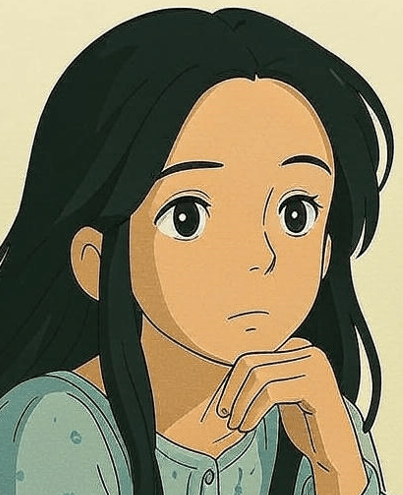
新築の場合は、
ハウスメーカーが表題登記や保存登記
の名義人になるの?

可能ですが、一般的には、
買主様名義で申請します。
「表題登記の名前」=「保存登記の名前」
は一致する必要があるため、ハウスメーカー→買主様
名義にすると余計な費用がかかります。
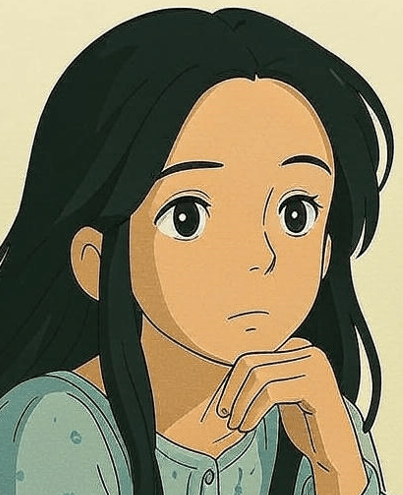
なるほど!
二度手間だし、
所有権移転登記とか
お金かけたくないわよね
引っ越し前に引っ越し?
住宅用家屋証明書の発行するために、
「新住所」に住所変更をしなければいけません。
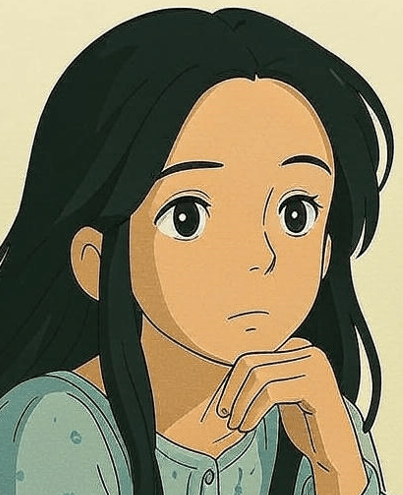
住んでいないのに?
どうして?

役所は減税にかかわる書類だから、住宅家屋証明の申請は厳しく確認します。
その時、住民票と新居が一致しているか、チェックするわけです。
自分が居住する証明、つまり、
引っ越しを「金消前までに」済ませておかないといけません。
※決済日に移転登記や抵当権権の登記があるため、その際に必要となります。

登記の申請時に、住宅用家屋証明書の添付が必要なので、
早めに住所変更を済ませておきましょう。
※金融機関にも指示されます。
例えば、新築建売は本審査の結果が出てから、
動き始めるハウスメーカーさんが多いです。
中古住宅は、売主さんの許可が必要です。
※居住中だと難しい
「子供の学区が・・・」と難しい場合、申立書の提出が必要です。
申請する家屋と住民票が不一致の場合、
申立書に理由を記載すれば、特例を受けられるケースがあります。
引っ越しの理由や、家屋の処分方法など証明書類が必要です。
<売買で住みかえる>
売買契約書・媒介契約書など
<アパートなど借家>
賃貸借契約、他賃貸の証明書など
引き渡し後に住所変更をすると、住所変更登記で費用が発生します。
子供の学区問題がなければ、先日住所を変更しておきましょう。

担当営業や司法書士の先生と事前に調整をしておきましょう。
住宅ローン減税の上限がアップ?!

住宅ローン控除は、年末の住宅ローン借入残高の「最大0.7%」が所得税から還付され、控除しきれないと住民税から還付されます。

2025年は最大4500万円です。
※認定長期優良住宅、低炭素住宅の場合
①認定長期優良住宅②認定低炭素住宅を取得した場合、
住宅ローン控除の手続きで「住宅用家屋証明書」が必要となります。

確定申告の提出時は、「コピー」でOKのようですね。
※提出前に確認願います。
住宅ローン控除については、税理士さんや税務署に確認してみてください。
→【一覧表あり】初めての住宅ローン控除! 必要書類や注意点は?
まとめ

住宅用家屋証明書のメリット
- 登録免許税の軽減: 新築は所有権保存登記(0.4%→0.15%)、
中古は所有権移転登記(2.0%→0.3%)、
抵当権設定登記(0.4%→0.1%)が軽減。 - 自己居住用住宅の税負担軽減: 新築・中古問わず、自己居住用の家屋取得時に節税可能。
- 手続きの明確化: 証明書により、住宅用途が公的に証明され、登記手続きがスムーズ。
住宅用家屋証明書のデメリット
- 申請の手間: 市区町村での申請に住民票や契約書等の書類準備が必要。
- 発行費用: 証明書発行手数料(数百円~1,300円程度)がかかる。
- 条件の制約: 床面積50㎡以上、居住用などの条件を満たさないと発行不可。
- 期限の制限: 取得後1年以内に登記申請が必要。
簡潔にまとめましたが、詳細は営業担当や市区町村など確認してください。
最後に住宅用家屋証明書は買主が取得。(住宅が所在する市区町村の役所・役場で発行)
そして、司法書士さん経由で、法務局に提出します。

住宅用家屋証明書について,あなたのお役に立てれば幸いです
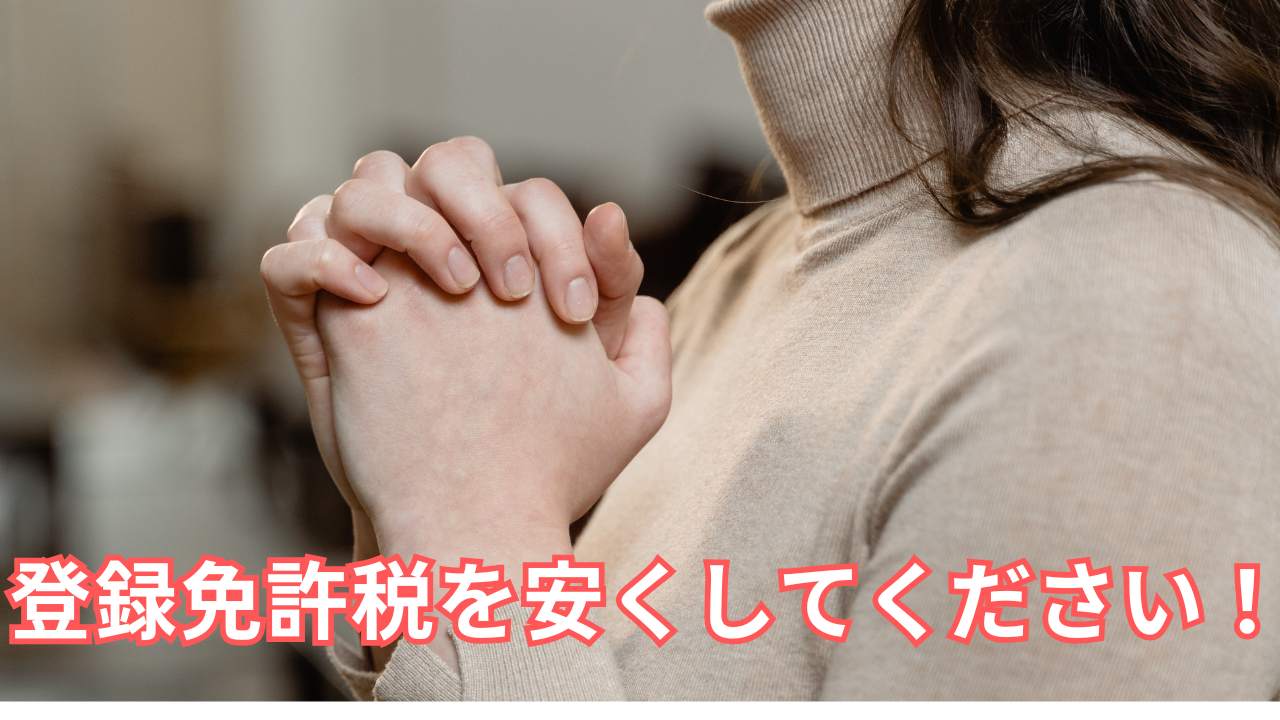



コメント