不動産売買契約書とは、不動産(土地・建物など)を売買する際に、売主と買主が締結する契約書です。

不動産売買契約には
「24の不動産売買契約条項」があり、今回は第2条売買対象面積
について解説します。
売買対象面積の解説
【全宅の契約書】
(売買対象面積)
第2条 売主及び買主は本物件の対象面積を標記面積(A)とし、実測面積との間に差異が生じても互いに異議を申し立てないとともに、売買代金増減の請求をしないものとする。
<やさしく翻訳>
売主買主双方、対象物件を表記面積とし、
実際に測量して数値に差異があっても、お互い文句は言いません。
土地の面積が実際測定したら、ズレがある・・・は日常茶飯事です。
※建物面積は差がないケースが多いです。
そのため、面積に差異が生じたときの
決まり事が必要です。
<土地>
「実際の土地の面積」と「登記簿・地積測量図」と差異はないか?
<建物>
「実際の土地の面積」と「登記簿・建物図面」と差異はないか?
公簿取引とは?
今回は「公募取引用」の売買契約書で解説しています。
登記簿上の面積を「公簿面積」と呼び、
その面積での取引を公募取引(売買)と言います。

登記済みの㎡数のまま
取引しましょう!
という意味です。
例えば、土地の登記簿に「100㎡」
実際に測量をしたら「85㎡」だったとします。

15㎡小さいの?!
私なら買わないかな

最初から分かっていれば、
買わないですよね。
しかし、売主や仲介会社によっては
「互いに売買代金の変更その他何らの請求もしません」
と書いてあるから、知りません!という人が多いです。

どうすればいいの?

簡易的ならiphoneのアプリで測れます。
土地家屋調査士に依頼すると10万円
以上かかりますが、
心配な場合、お願いしましょう。
通常、売主負担ですが、人気の土地の場合は、
買主負担となることがあります。
参照元:土地家屋調査士「チロ太」様より参照
実測取引とは?
「実測取引」とは、土地家屋調査士や測量士に測量を行い、
その測量面積で価格を決定して取引を行います。
※「実測・清算型」の契約書を使用します。
→仮測量・現況測量とも呼びます。

売買契約を締結し、仮測量を1日で終えます。
※資料作りを含めると4日ほど
仮測量の料金は10万円~15万円ほどです。
売買契約を交わし、そのあと、実際に測量し、
測量面積 > 公募面積
測量面積 < 公募面積
公募よりも広ければ、清算金が高くなり、
逆に狭ければ、安くなります。
【例:清算金の計算】
公簿面積100㎡、単価10,000円/㎡
→実測面積が95㎡の場合、5㎡×10,000円
差額5万円を決済日に売主へ精算します。
実際の現状は?
公募売買(固定型)の土地取引が多いです。
例えば、最近空き家問題で相続人が田舎の土地や建物を相続します。
すると、「測量とか面倒だし・・・」
と現状有姿・境界不明・契約不適合責任免責で売却します。

買主としては、
仮測量するか、
確定測量したいわ・・・

確定測量がおすすめです。
が、理想と現実は異なります。
坪50万円以上など高額な取引の場合は、確定測量がおすすめですが、
田舎の土地の場合、公募売買(固定か清算)取引が多いです。
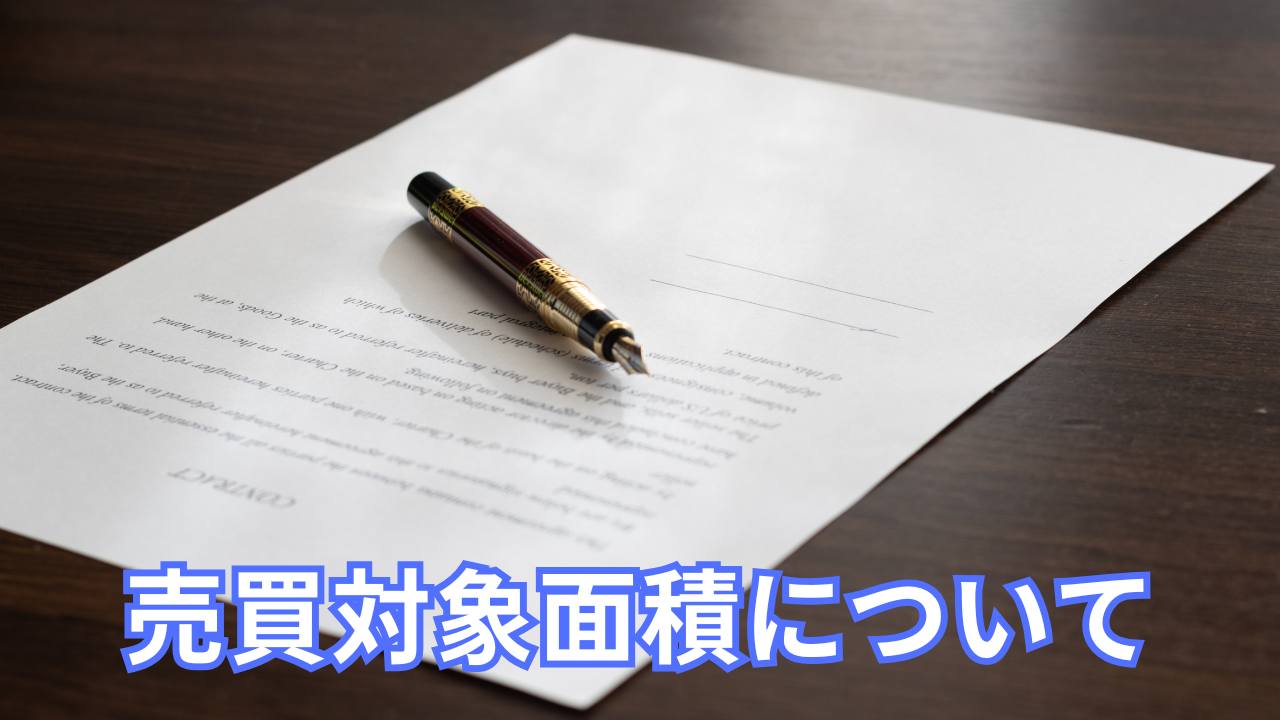



コメント