
住宅ローンの審査は金融機関が判定するんじゃないの?
住宅ローンは金融機関の窓口で相談受付しますが、
最終的に保証会社が審査の結果を判定します。
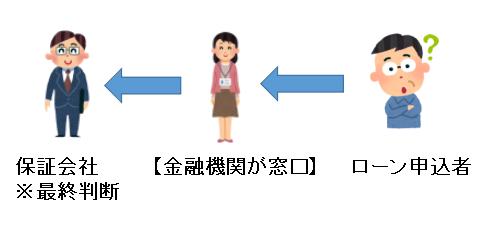
今回は保証会社について詳しく解説しますね。
住宅ローン審査は「保証会社」がジャッジ?!
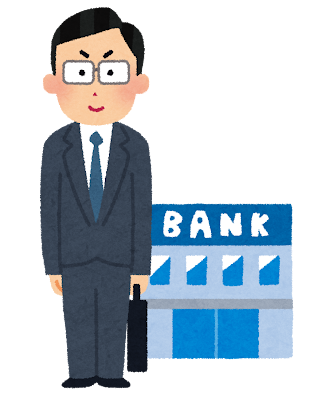
銀行があなたに住宅ローンを融資し、
回収できないと銀行は困りますよね?
そこで銀行が住宅ローンを回収できないときに、
代わりに保証をする会社が保証会社です。

賃貸アパートと似ていて、大家さんが家賃回収できない場合、
賃貸保証会社が代りに負担します。
※賃貸借契約の時に、保証会社へ申し込みをした人も多いはずです。
大家さんが安心して賃貸経営できることと同じで、
銀行も安心してあなたにお金が貸せます。
昔は親や兄弟に保証人になってもらいました。
しかし、現在は「保証会社を付けるケース」がほとんどです。
保証会社は何種類あるの?

保証会社といっても、何社?何種類あるのか? 解説します。
①全国保証
全国保証株式会社が提供する「全国保証」
日本全国のほとんどの銀行か利用しています。

一般的に審査は「ゆるい」と言われ、ここで否決されるとかなり厳しいです。
保証料を顧客から受け取り、40年以上のノウハウとデータ活用で業界トップクラスの実績を誇ります。
保証債務残高は17兆円超で、国内最大級の住宅ローン保証会社です。
②しんきん保証基金
全国の信用金庫が利用しています。
「国民生活の安定と向上に資する」ことを事業の目的として設立された
信用金庫業界の個人向けローン専門の 「信用保証機関」です。
※個人が信用金庫から住宅ローンなどを借りる際、
しんきん保証基金が保証人となり、借り入れを円滑にします。
これにより、顧客の信用力を補完し、融資を受けやすくします。

IO信用金庫、高崎信用金庫、川口信用金庫、埼玉縣信用金庫・・・・
などで住宅ローンを組む
場合にしんきん保証基金が保証をします。
※一般的に審査は「少しゆるい」と言われます。
③銀行の子会社、系列グループの保証会社
りそな保証、関西みらい保証など銀行グループで独自の保証会社を運用しています。
審査はやや厳しめ、といえます。
④地方銀行の保証会社
地方銀行の独自の保証会社です。
⑤フラット35(住宅金融支援機構)
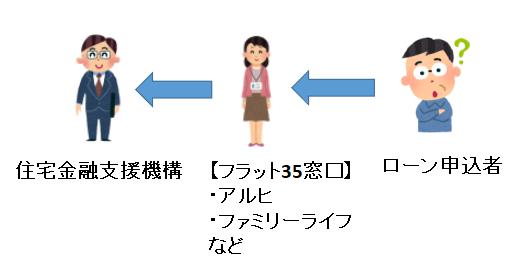
住宅金融支援機構が保証をしてくれます。
全国保証否決の場合は、フラット35への申込がおすすめです。

住宅金融支援機構は住宅購入を応援してくれる機関です。
他保証会社は冷たくても、機構が積極的に融資をしてくれるため、
ダメならフラット35がおすすめ。
⑥独自系(MG保証・ろうきん、JA)
①MG保証:2019年頃に登場したばかりのMG保証。
主に二次保証として使われ、返済比率が最大55%と融資金額が伸びやすいです。
→MG保証について
②ろうきん:労働金庫の保証会社は独自のため、労組の組合員の場合、審査がゆるくなりがち
(一社)日本労働者信用基金協会(日本労信協) (株)オリエントコーポレーション のいずれかの保証会社の利用となります。

日本労信協は審査がやや緩めです。
労働者のための非営利企業なので、クレジットヒストリーに多少問題があっても、
大目に見てくれる傾向が高いです。
→ろうきんの住宅ローン審査は甘いって嘘?
③JAバンク:農協の銀行です。
JA連携の保証会社(農業信用基金協会・協同住宅ローン㈱・全国保証㈱)などで
農業信用基金協会はJA独自といえます。
保証会社を受ける優先順位はある?
独自の保証会社で審査否決→外部の全国保証、
または審査が緩いMG保証などと審査が流れていきます。

A銀行(全国保証)で否決されたら、
B銀行(全国保証)へ申し込んでもローンは否決されます。
※銀行は異なりますが、
保証会社が同じ場合は情報が共有されています。
住宅ローンの保証料とは?

住宅ローンを契約する人が保証会社と保証契約を結ぶ際にかかる費用です。
※賃貸アパートを借りるときの「賃貸物件の保証料」と似ています
住宅ローン保証料はいくら?
住宅ローン保証料は2種類あり、支払い方法が異なります。
簡単にいうと、
①一括で前払い
②毎月のローンに金利上乗せ払いの2種類
です。
①保証料の支払い方「前払い型」
住宅ローンの借入額の2.2%程度を保証金として前払します。
例:3000万円なら66万円ほど

長期間のローンの返済であれば、前払いがおすすめです。
②保証料の支払い方「金利上乗せ型」
住宅ローンの毎月返済に金利0.2%ほど上乗せして支払います。
例:3000万円で35年払いなら、月3000円ほど
初期費用を抑えるなら、上乗せ型がおすすめです。
ただし、返済期間が長いほど、金利負担が重く感じます。
保証料がかかる理由は?
保証料は保証人がいれば、昔は不要でした。

現在は保証会社が「銀行の」保証をするため、
保証料を払わないとローン契約ができません。
保証料が0円の銀行はある?
あります。
新生銀行やフラット35、住信SBIやソニー銀行などは保証料がありません。

え?安くていいんじゃない?
ローン保証料はありませんが「手数料2.2%」はあります。
つまり、名前が異なるだけで、実質「保証料」というわけです。
一般的な銀行の保証料と事務手数料
三菱UFJ銀行
- 保証料:保証会社(三菱UFJ住宅ローン保証など)を利用。借入金額3,000万円、35年返済で約50~80万円(一括前払い)または金利上乗せ(0.2~0.3%程度)。
- 事務手数料:定額型で3.3万円(税込)。保証料型が基本のため、事務手数料は低め。
- 特徴:保証料の一括払いと金利上乗せを選択可能。
メガバンクとして保証料型が主流。
みずほ銀行
- 保証料:みずほ信用保証など利用。
借入3,000万円、35年で約40~70万円。
一括前払い、分割払い、または一部前払い+金利上乗せの3プランから選択。 - 事務手数料:定額型で3.3万円(税込)または定率型(借入金額の2.2%)を選択可能
- 特徴:保証料の支払いプランが柔軟。
融資手数料型も選択可で、ネット銀行のような高額手数料プランも提供。
りそな銀行
- 保証料:りそな保証を利用。借入3,000万円、35年で約50~80万円。
一括前払いまたは金利上乗せ(0.2~0.4%) - 事務手数料:定額型で5.5万円(税込)。保証料型が基本
- 特徴:繰上返済時の保証料一部返還あり。保証料の一覧表を公開し、透明性が高い。
住信SBIネット銀行
- 保証料:無料(保証会社を利用しない)
- 事務手数料:定率型で借入金額の2.2%(税込)。
例:3,000万円で66万円。 - 特徴:融資手数料型が主流。保証料不要だが、手数料が高額
初期費用をローンに組み込む選択肢あり。
auじぶん銀行
SBI新生銀行
- 保証料:保証会社利用の場合、借入3,000万円で約40~70万円。
一括前払いまたは金利上乗せ。保証料不要のプランもあり。 - 事務手数料:定額型(5.5万円~11万円)または定率型(借入金額の1.1~2.2%)。
- 特徴:保証料型と融資手数料型の両方を提供。
2024年10月で定額型の一部プラン終了。柔軟な選択肢が特徴。
地方銀行(例:筑波銀行、足利銀行)
- 保証料:全国保証やしんきん保証基金を利用。
借入3,000万円、35年で約50~100万円。金利上乗せも選択可。 - 事務手数料:定額型(3.3~5.5万円)が一般的。保証料型が主流
- 特徴:地域密着型で保証料型を採用。保証料が高額だが、繰上返済で返還の可能性あり。
まとめ

・住宅ローン審査は最終的に「保証会社」が決定権あり
・全国保証も最も利用され、審査がややゆるい
・保証料は①一括払い②金利上乗せの2種類
・保証料は融資金額から引かれて振り込み

保証会社が気になるあなたのお役に立てれば幸いです






コメント