長期優良住宅の基礎を学ぶ
長期優良住宅とは、
長期に渡り良好な状態で使用するための条件を満たし
「認定された」住宅のことです。
・・といっても意味不明ですよね?
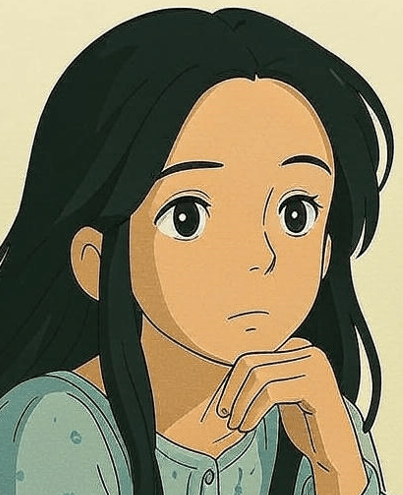
うーん、
よくわからない

要は
「丈夫で長持ちで、
長期間住み続けられると国から認められた住宅」
と言う意味です。
スクラップ&ビルドの期間を長くする
日本は中古住宅が嫌いで、
新築が大好きな民族です。
<令和3年度住宅経済関連データ:滅失住宅の平均築年数>
・イギリス:78.8年
・アメリカ:55.9年
・日本:38.2年
日本の住宅は約38年で解体(スクラップ)し、
新築を建築(ビルド)します。
そこで長期優良住宅(※)のような「長持ちする家」を作り、
イギリスのように70年以上で解体したほうが、
お財布&環境にも優しいといえます。
※2025年現在で長期優良住宅は
4棟に1棟が認定されています。
まだまだ認定数は少ないといえます。
認定基準は8つ

①劣化対策
劣化対策等級3相当+追加措置が必要です。
床下に点検スペースのための高さや小屋点検口を設ける必要ががあります。
費用が多くかかる点は防蟻処理で15万円ほど発生します
②耐震性
耐震等級2(許容応力度計算)で適用されます。
できれば耐震等級3(許容応力度計算)をおすすめします。
※耐震等級「1」と比べて「3」は60万円ほど
別途発生します。
③省エネルギー性
断熱等級5(ZEH)まで性能をアップしましょう
※太陽光発電の発電は無関係です。

断熱材の厚みが増すため、
断熱等級が上がるほどコストアップします。
④維持管理・更新の容易性
維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うための
施工です。
例えば、コンクリート内に専用配管を埋設しないようする、など
⑤居住環境
地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の
計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、
これらの内容と調和を図ります。
⑥住戸面積
戸建ては75㎡以上(※約22.7坪)かつ
階段部分を除いて1階の床面積が40㎡(約12.1坪)以上
⑦維持保全計画(アフターメンテナンス)
耐力上主要部分・雨水侵入部分・給排水設備について
認定時から30年以上のメンテナンス計画を提出。
⑧災害配慮
「土砂災害、津波、洪水などの
災害リスクが高い区域が所管の行政内において
既に指定されている場合、その区域で認定を行う際に配慮を求める」
長期優良住宅の申請費用は?
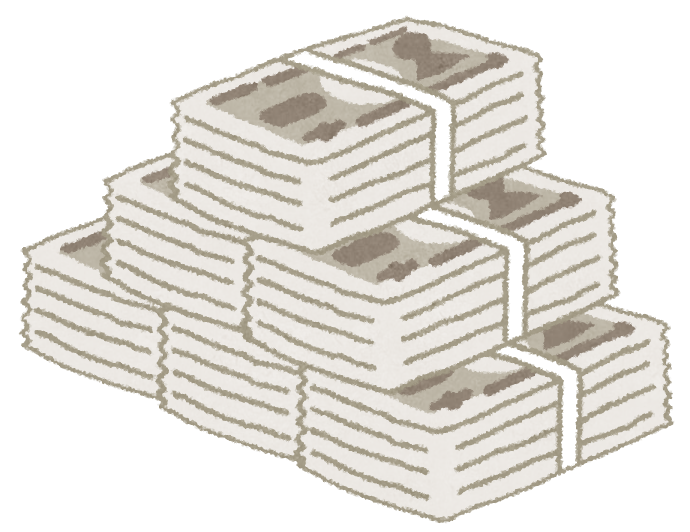
長期優良住宅の申請・審査にかかる費用はおおよそ5~6万円。
実際はハウスメーカーに申請書類を作成、
認定申請の申し込みなど
合計で15万円~40万円程度かかります
【長期優良住宅の申請費用の目安】
| 内容 | 費用の目安(概算) | |
| 設計・申請手数料 | 設計事務所や工務店に支払う手数料。申請書類の作成、必要な性能計算(構造・省エネなど)を含む。 | 約10万~30万円程度 |
| 技術的審査手数料 | 登録住宅性能評価機関に支払う、技術的な確認・審査費用。 | 約5万~10万円程度 |
| 認定申請手数料 | 自治体に支払う申請料(行政の審査費用)。自治体によって異なる。 | 約1万~3万円程度 |
| 合計 | すべてを合算した申請費用の総額 | 約15万~40万円程度 |
長期優良住宅のメリット

長期優良住宅のメリットを8つ解説します。
①付加価値がアップする
長期優勝住宅にすれば、
将来売却する際、「この家は国の厳しい審査に合格した家です」
と地震をもって、売り出せます。
買主は安心ですし、古くても人気があるため、
相場以上で家が売れるかもしれません。
②住宅ローン減税効果が大きい
ローン控除対象限度額最大4,500万円まで対象です(最大13年)
また、最大控除額は409.5万円と、かなりオトクです。

1年間で控除できる金額の上限は4,500万円×0.7%=31.5万円
13年間の合計は31.5万円×13年=409.5万円
③登録免許税の税率が下がる
登録免許税:土地が買主に移転される移転登記。
新築の建物が初めて登録される保存登記などがあります。
長期優良住宅の認定を受けると、
税率の軽減が受けられます。
| 控除率 | |
| 保存登記費用 | 0.15%→0.1% |
| 移転登記費用 | 0.3%→0.2% |
| 移転登記費用(マンション) | 0.3%→0.1% |
例:2500万円の建物を例にします。
保存登記費用 0.15%(37,500円)→0.1%(25,000円)
移転登記費用 0.3%(75,000円→0.2%(50,500円)
マンション(移転) 0.3%(75,000円→0.1%(25,000円)
④不動産取得税の控除アップ
土地・建物等など新築や売買、
または贈与や相続などで取得した場合にかかる税金(3%)です。
一般住宅1,200万円→認定長期優良住宅 1,300万円
例:2500万円の建物を例にします。
・一般:2500-1200=1300万円×3%で39万円
・長期優良住宅:2500-1300=1200万円×3%で36万円
→3万円不動産取得税の減税効果があります。
⑤固定資産税の減税措置が3年間→5年間
固定資産税は固定資産税の評価額の1.4%です。
※土地、建物両方にかかります。
<一般住宅>3年間1/2
<一般住宅>5年間1/2
例えば1年で15万円恩恵があれば、
長期優良住宅は2年延長されるため、
30万円もオトクになります。
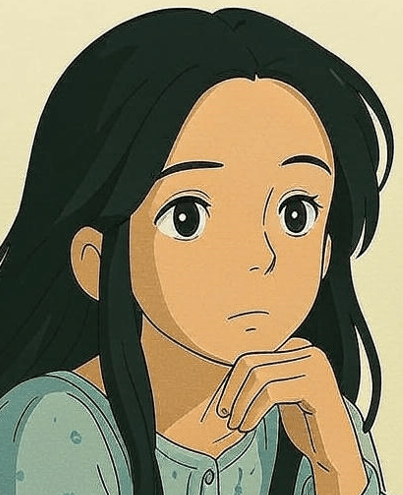
地味だけど、
5年間1/2は
節約できてうれしい!
⑥地震保険料が最大50%OFF
- 耐震等級2は30%割引
- 耐震等級3は50%割引
⑦フラット35のSプランで優遇あり
フラット35で住宅ローンを申し込むとき
フラット35Sというプランがあります。
<長期優良住宅の金利優遇>
■1年目~5年目 0.5%引き下げ
■6年目~10年目 0.25%引き下げ
例えば3,000万円の借り入れで
①金利1.9%で月9.8万円
②金利が0.5%下がると1.4%で月9.1万円
→月7,000円、年間84,000円も返済額が下がります(5年間)
⑧補助金あり
長期優良住宅の認定を受け、
条件を満たすと、補助金が貰えるケースがあります。
①地域型住宅グリーン化事業(新築)
資材供給、設計、施工などの連携体制により、
地域材を用いて省エネ性能等に優れた木造住宅(ZEH等)
の整備等に対して支援を行います。
●支援対象:地域の中小工務店のグループの下で
行われる省エネ性能に優れた木造住宅の新築。
●限度額:140万円/戸 等
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shienjigyo_r5-01.html
長期優良住宅のデメリット

長期優良住宅のデメリットを3つ解説します。
①着工するまで約2か月かかることも
省エネ計算、耐震等級、書類作成があるため、
書類準備や申請プロセスが多いです。

着工するまで2か月かかることあるため、
引き渡しまでの余裕がないと、
キツイかもしれません。
点検費用がかかる
新築後、5年・10年・20年・30年のタイミングで
維持点検の義務(※)があります。
点検費用は30年で15万円~20万円かかるため、
メンテナンス費が高額です。
※任意でなく、義務です
建築コストアップ
耐震等級3や防蟻処理、断熱等級アップ、
書類申請など、建築コストがあがります。
長期優良住宅はよい家とは限らない?

令和の時代で、通常の新築を作っても、
長期優良住宅なみの基準で家が立ちます。
長期優良住宅の申請時間や建築コストアップを考えると
「ZEHでいいのでは?」という意見もあります。
※ZEHも住宅ローン控除などあります。
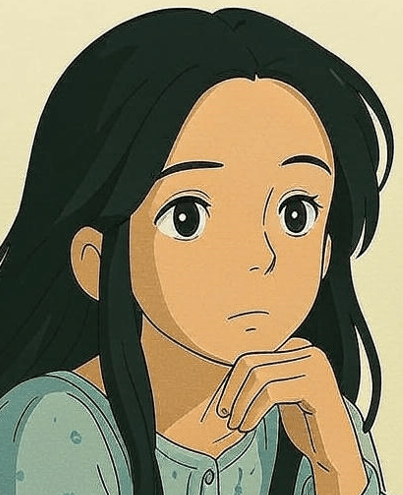
長期優良住宅は、
登録免許税が節税できたり、
控除で少し得だったりするけど、
申請に時間がかかるし、
お金もかかるから・・・
なんともいえないかな?

筆者は地元工務店で建築しました。
長期優良は取らずに
長期優良住宅の基準になるべく一致する
設計&建築をしてもらいました。
まとめ

| メリット | デメリット | |
| 耐震性能 | 耐震等級2以上で地震に強い | 建築や申請コストが やや上がる |
| 省エネ性能 | 光熱費の削減・断熱性能が高い | 高性能な断熱&厚みが必要 |
| 資産価値 | 中古市場で高評価になりやすい | 認定の維持・管理が必要 |
| 減税措置 | 固定資産税の軽減、住宅ローン控除の拡充 | 手続きが煩雑で時間がかかる |
| 維持管理 | 将来のメンテナンス計画が明確 | 書類整備・維持管理記録が必要 |
| 補助金・融資優遇 | フラット35の優遇、各種補助金対象 | 補助金対象にならないケースもある |
| 長寿命化 | メンテナンスコストが低減しやすい | 施工に高品質が求められ、費用が増す |
| 住み心地 | 温度差が少なく快適な住環境 | 仕様制限により自由設計が制限される場合あり |
| 地域優遇 | 一部地域での優遇制度・条例対応が可能 | 対応できない地域や業者もある |
| 設計・施工の安心感 | 審査機関による厳格なチェックで安心 | 審査・認定に時間がかかる(1~2ヶ月) |
長期優良住宅の認定制度について、
あなたのお役に立てれば幸いです。






コメント