銀行選びで失敗しない6つのポイント
住宅ローンで「銀行選びで失敗しない方法を6つご紹介します。
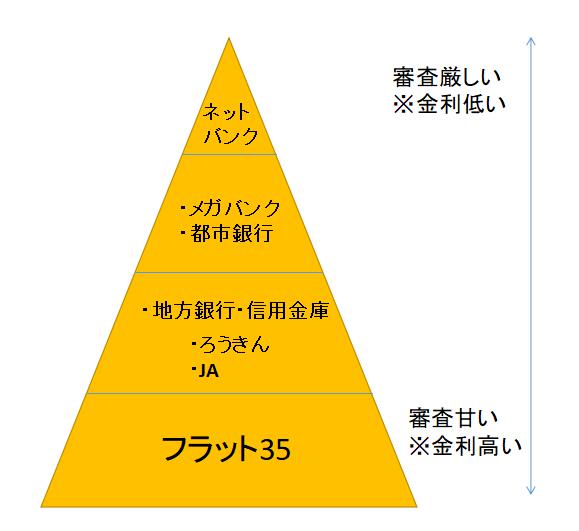
ネットバンクなど、上に行くほど、審査が厳しい&金利低くなり、優遇されます。
逆に
下に行くほど、審査は優しくなりますが、金利が高くなります。
①銀行の特徴を抑える
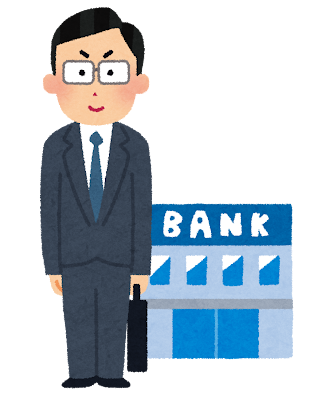
信用金庫・信用組合
地元密着の銀行。
取引先を店舗近くの中小企業・住民等とし、
域外の企業・個人には融資をしません。
例:アイオー信用金庫 高崎信用金庫 埼玉縣信用金庫など
<強み>親身になって相談してくれる。
個信にキズあり、個人事業主などの属性でも相談にのってくれる
<弱み>金利がやや高い
地方銀行
<関東の地方銀行一覧>
- 群馬銀行
- 武蔵野銀行
- 横浜銀行
- 足利銀行
- 千葉銀行
- 山梨中央銀行
- 常陽銀行
- 千葉興業銀行
- 筑波銀行
- きらぼし銀行
<強み>
・地元に密着している。ローンセンターが多い
・審査もやや緩め(銀行による)
<弱み>
金利がやや高い
メガバンク
メガバンクは、三菱UFJ、三井住友、みずほ、りそな、埼玉りそななどです。
<強み>
・全国の幅広いエリアをカバーしている。
・住宅ローンプランが豊富など
・金利が安い
<弱み>審査がやや厳しい
ネットバンク
auじぶん銀行、ペイペイ銀行、楽天銀行、住信SBIなど
<強み>
・金利が格安
・WEB申し込みが手軽
・直接売主口座へ融資できる
<弱み>
・審査がかなり厳しい
・審査が遅い
JAバンク
農協が運営する銀行です。
<強み>住宅ローンが車ローンとまとめられる、最大40年融資あり
<弱み>審査がやや緩い
ろうきん
労働金庫、略してろうきんです。
営利を目的としない働く仲間が作った金融機関
<強み>
・労働者に優しい
・労働組合員はかなり優遇される
・属性やCICにキズがあっても、
多少目をつぶってくれる
・最大40年融資
<弱み>
労働組合員かCOOPの会員でないと、申し込めない
フラット35
民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する
最長35年の全期間固定金利の住宅ローン
<強み>
・実行金利と審査金利がほぼ同じ。
・CICにキズがあっても、多少目をつぶってくれる。
・融資額が伸びやすい
・営業マンの間で「最後の砦」と言われている
・個人事業主の味方
・団体信用生命保険は任意(※健康状態で問題がある人)
<弱み>
・固定金利のみで、変動金利で申し込めない。
・中古不動産の融資が苦手
②申込者の属性(職業)

申込者の職業によって、選ぶ銀行が変わります。
<職業別のおすすめ銀行>
①公務員:どこでもOK。ネットバンクが通る可能性大
②会社員(一部上場):どこでもOK。ネットバンクが通る可能性大
③会社員(中小企業):ネットバンクは厳しいが住信SBIや地銀がおすすめ
④派遣社員/契約社員:フラット35、ろうきん、JA、住信SBI
⑤自営業者:フラット35、JA、信用金庫
⑥会社経営者/役員:フラット35、JA、信用金庫
③融資期間(※完済年齢)

金融機関によって、完済時の上限年齢は異なりますが、80歳未満が一般的です。

44歳まで申し込むと35年住宅ローンが組めます。
それ以降は融資年数がどんどん短くなります。
最近は住信SBIやフラット50など、最大50年ローンがあります。
年齢は29歳まででマックス50年組めます。
| 返済期間 | 35年 | 50年 |
| 金利 | 0.80% | 0.80% |
| 借入金額 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 毎月返済額 | 88,285円 | 66,073円 |
| 総返済額 | 約3,707万円 | 約3,964万円 |

なるほど。
融資期間が延びるほど、
毎月の返済額が増えるのね。
④総返済額(いくらまで借りられる?)

「住宅ローン、私はいくら借りられる?」
<ざっくり計算>
■フラット35:年収の8~10倍
■その他:年収の7~8倍
次は「自分で計算」してみましょう。
<仮のケース:夫年収370万円>
※借入:カードローン50万円で
「月返済1.5万円(年18万円)」とする
→フラット35 審査金利1.9%
<返済比率(審査金利)>
返済比率=年返済108万円÷年収370万円=29%
<返済比率(審査金利+既存借入)>
返済比率=
(年返済108万円+年返済18万円)
÷年収370万円=34%
<借り入れの3パターン。②③で判定します。>
※例:フラット35↓
※2700万円不動産を35年返済フルローン
①返済比率(実行金利1.9%)29%
②返済比率(審査金利1.9%)29%
③返済比率(審査金利1.9%+既存借入)34.18%

なるほど。
カードローンとか
既存の借入があると
返済比率が悪化するのね・・・
■フラット35返済比率
30%未満(年収400万円未満)
35%未満(年収400万円以上)
年収が370万円ですと、
審査落ち(30%未満でない)します。

既存の他社借入が多いと、審査落ちするかもしれません。
詳細な計算は担当者にお問い合わせください
返済比率を良くする方法
①奥さんや両親と収入合算
奥さんがパートで年70万円ほど年収があれば、
世帯年収が440万円。
返済比率=(年返済108万円+年返済18万円)÷年収440万円=28%
と数値が改善するため、
審査通過率がアップします。
また、奥さんが専業主婦なら、
両親(奥さんの両親含む)と親子リレーローン(フラット35)がおすすめ。
※同居は不要!!
②返済年数を伸ばし、月返済負担を減らす
フラット35・アルヒの場合MG保証(最大50年)
他では、住信SBI銀行最大50年、JAろうきん40年などがあります。
③借り入れ金額を減らす
審査金利が厳しい(例:変動0.8%でも審査金利3.5%など)場合は、
頭金の入れて返済額を減らしましょう。
⑤金利タイプ(変動金利・固定金利)

住宅ローンを借りるとき、
必ず元金と金利の返済があります。
■固定金利:1.9%ならずっと毎月の返済が一定(フラット35など)
■変動金利:借入期間中に適用される適用金利が変動
変動金利は市場金利の動きに関係なく、
借入開始から「5年間は返済額が固定」されます

5年ルール:変動金利が上がっても、月々の返済額を5年間一定とするルールです。
5年ルールは返済額が固定されますが、金利と元金の内訳は変化します。
※住宅ローンアナリスト塩澤さんのちゃんねるより
変動金利のメリット・デメリット
<変動金利メリット>
安い金利で「返済額を抑えたい」
<変動金利デメリット>
借入額が多く、金利上昇で破産リスクがある
<固定金利メリット>
返済の見通しを立てやすい
<固定金利デメリット>
現時点で金利が高い

フラット35の申し込みでなければ、
筆者は変動金利を推奨します。
| メリット | デメリット | |
| 金利 | 初期金利が固定金利より低い場合が多い | 金利上昇により返済額が増える可能性がある |
| 返済額 | 金利が低ければ毎月返済額を抑えられる | 金利変動で返済額が予測しにくい |
| 柔軟性 | 金利低下時に返済負担が軽減される | 将来の返済計画が立てにくい |
| 適用条件 | 審査が比較的通りやすい場合がある | 金利上昇リスクに備えた資金計画が必要 |
⑥団体信用生命保険料&がん特約など

団体信用生命保険(団信)は住宅ローンの契約者に死亡、
高度障害を負った場合、負債がチャラになり、家族や家を守ることができる保険です。
健康状態に問題がなければ、加入をおすすめします。

団信の支払い方法は2つ。
①一括で前払い
②金利に上乗せ(+0.2%など)
ガン保障はできればつけましょう。
例えば住信SBIは、
がんを含む病気やケガが手厚くカバーできる「全疾病保障」が基本付帯しています。
金利がプラスになったり、デフォルトで付帯している金融機関もあります。
ちなみに、ガン特約の加入はおすすめします。
※申し込み時しか加入できません。
カーディフ生命の「生活価値観・住まいに関する意識調査」にはガン特約に加入しておけばよかった、が39%います。

旦那さんは
病気がちで、健康診査によく引っかかるの・・・
入れるかしら?

ケースバイケースです。
①ワイド団信
金利が高いですが、健康状態にやや不安がある人向けの団信
②任意のフラット35を選択
の上記2通りです。
住宅ローンのよくあるQ&A

住宅ローンでよくある質問をQ&A形式にしました。
- Q住宅ローン申込にかかる費用は?
- A
①ローン事務手数料・保証料
②印紙代(※金消の時)
ローン事務手数料・保証料は
「手続きの手数料だったり、保証会社に支払うお金です。」

保証会社は、あなたがローン返済できなくなったときに、
銀行に代わりに支払ってくれる会社です。
アパート申し込み時の、家賃保証会社に似ています。
①ローン事務手数料・保証料:「借入金額×2.2%」
②印紙代(※金消の時):借入額による(※2万円が多い)
ちなみに、「ローン代行手数料」を取る不動産業者は注意が必要です。
以下は2850万円の不動産を購入した場合の内訳です。
※あくまで概算です。
保証料はなくても「事務取扱手数料」などの名目で
取られる金融機関もあります。
【住信SBI銀行で借りた場合】
| 項目 | 目安金額(円) | 備考 |
| 事務取扱手数料 | 627,000 | 借入金額2850万円 × 2.2%(税込)。 融資額に応じた定率型。 |
| 印紙税 | 0 | WEB契約の場合、契約書に印紙不要。 |
| 登録免許税 | 114,000 | 抵当権設定費用。借入金額2850万円 × 0.4%。 |
| 司法書士報酬 | 100,000 | 登記代行手数料。目安として10万円前後。 |
| 火災保険料 | 150,000~350,000 | 建物の構造や保険プランによる。木造の場合高め、10年分で試算。 |
| 不動産仲介手数料 | 943,800 | 物件価格2850万円 × 3% + 6万円(税込10%で試算)。 |
| 固定資産税清算金 | 50,000~100,000 | 引き渡し日までの分を日割り清算。物件や時期により変動。 |
| 水道負担金 | 50,000~200,000 | 自治体や水道管の仕様による。 |
| 合計(目安) | 2,034,800~2,584,800 | 物件価格の約7~9%程度。 |
- Q金消って何をするの?
- A
「ローンの条件はこれでよろしいでしょうか」の最終確認&契約です。
「金消(きんしょう)」とは、「金銭消費貸借契約」の略で、
住宅ローンを借りる際に金融機関と締結する正式な契約を指します
<金消契約の手順>
①契約内容の確認:
借入金額、金利タイプ(固定・変動)、返済期間、月々の返済額を確認。
抵当権設定や団信(団体信用生命保険)の加入条件も確認する。
金融機関から提示された契約書を読み、疑問点があれば質問。
②必要書類の提出・準備:
身分証明書、収入証明書(源泉徴収票や確定申告書)、印鑑証明書、住民票など。
不動産の売買契約書や重要事項説明書も必要。
金融機関によっては事前に書類を提出済みの場合も多い。
※住所は事前に新住所へ変更
③契約書への署名・押印:
金銭消費貸借契約書に署名し、実印で押印。
抵当権設定契約書にも署名・押印
(不動産を担保にする契約)。
一部金融機関では電子契約も可能(例:SBI新生銀行)
④当日の流れ:
金融機関の店舗に来店する場合、対面で説明を受けながら手続き。
司法書士が同席し、抵当権設定や登記手続きの説明を行うこともある。
電子契約の場合は、オンラインで書類確認・署名を行う。
- Q抵当権とは?
- A
住宅ローンなどでお金を借りるときに、購入する不動産に金融機関が設定する権利
※戸建ては土地&建物に抵当権が設定されます。
- Q住宅ローン金利はいつ確定?
- A
フラット35は融資実行時の金利
他金融機関:「申込時金利」か「融資実行時金利」です
※担当者にご確認ください
まとめ

①銀行の特徴を抑え、申し込みをする
②申込者の属性(職業)によって金融機関が異なる
③融資期間は最大35年~50年あり
④総返済額(いくらまで借りられる?)
⑤金利タイプ(変動金利・固定金利)を把握
変動金利で申し込みが多い(低金利のため)
⑥団体信用生命保険料&がん特約など
※フラット35は団信は任意

あなたの住宅ローン選びでお役に立てれば幸いです。
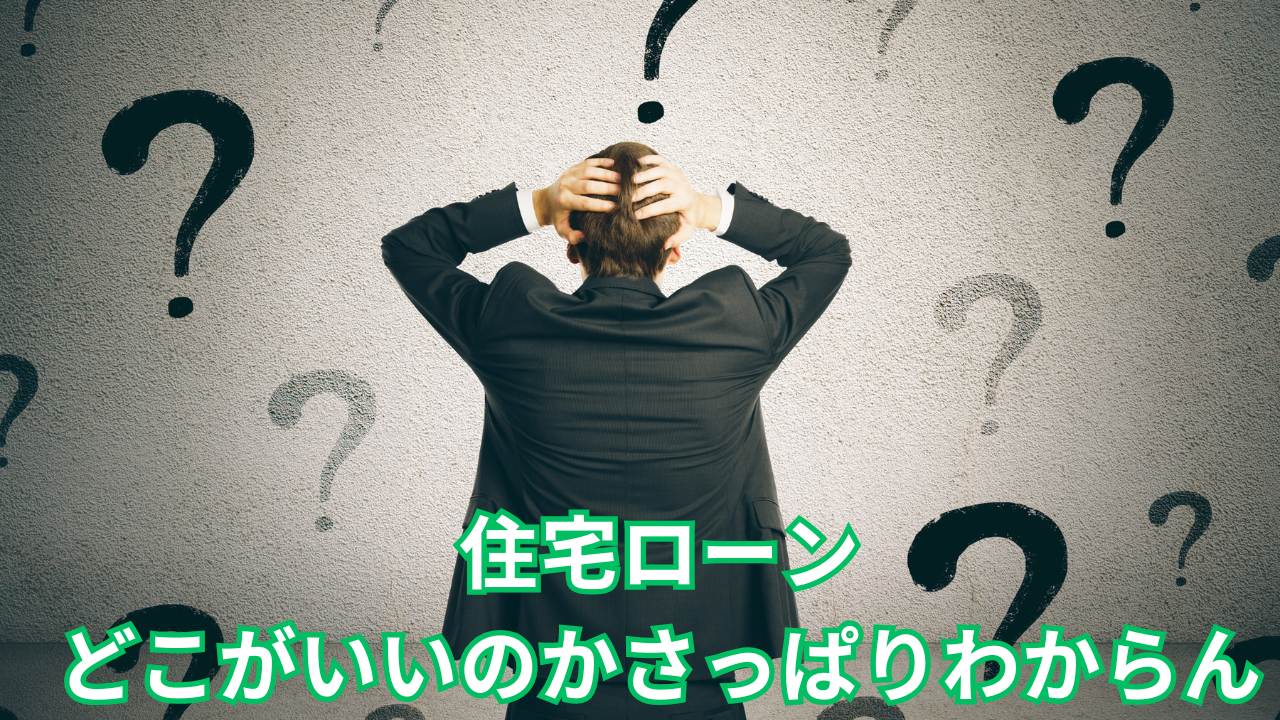





コメント